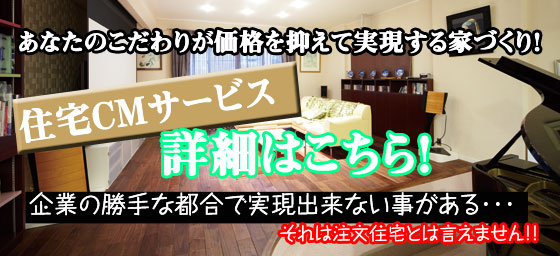家づくり関連ニュース
弊社が会員として参加している、(一社)健康省エネ住宅を推進する国民会議が主催となり、
弊社が事務局として参加している、おおさか健康省エネ住宅推進協議会が共催で、
大阪府さんに後援頂いた、「健康と住まい」との関連性に関するシンポジウムを開催致します。
「大阪の住宅と住まい方から日本1の健康長寿推進を目指して」
と、言うサブタイトルで、大阪に適した「健康的な住まい」とはどんなものかを話合います。
また、今後10年(当初3年)に渡って、国の補助事業として行われる、
家の断熱性能と健康との関連性についての調査事業の紹介も行われます。
こちらは、これからリフォームをする人などを対象に、調査協力者を募集します。
リフォームに掛かる費用の半額又は最高120万円までの補助が出る調査事業です。
詳細を知りたい方は、是非ご参加下さい。
【趣旨】
大阪府において、2000年にシックハウスを考える会(現健康・省エネ住宅を推進する国民会議)が
大阪府医師会の協力のもとに行った疫学調査が国を動かし、
シックハウス対策に関する建築基準法の立案にまで至りました。
今回、新たに全国の医学・建築の専門家がタッグを組んで、
「スマートウエルネス住宅等推進事業」による疫学調査が開始される事となりました。
この疫学調査では、住宅の温度環境を改善することが、どれだけ健康に寄与するのかを調べます。
(一社)健康省エネ住宅を推進する国民会議は今回の疫学調査の意義や目的を広く啓発するための中心的役割を担う事になりました。
今回のシンポジウムは、疫学調査やリフォーム補助を含めた事業の内容を広く大阪府の医学、
建築学の専門家および行政関係者、大阪府民に知っていただくことが目的で、
府民の協力の元に住宅の断熱性能が健康に与える影響を調査解明し、
大阪に適した住宅や住まい方を将来的に見つける事が、
大阪府民の健康長寿や若年者の健康維持につながる可能性について、議論致します。
【主催】 一社)健康・エネ住宅を推進する国民会議
【共催】 おおさか健康・省エネ住宅推進協議会
【日時】2014年10月19日(日) 15:00~
【場所】 グランキューブ大阪(大阪国際会議場)10F会議室
〒530-0005 大阪市北区中之島5-3-51
【内容】
1 趣旨説明 一社)健康・省エネ住宅を推進する国民会議 理事長 上原裕之
2 開会挨拶 おおさか健康・省エネ住宅推進協議会会長 杉田隆博
3・基調講演 慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科教授 伊香賀 俊治氏
「住宅と住まい方と健康に関する啓発、調査を大阪府民 全体で行い、健康長寿・地域活性化の国のモデルに」
4・来賓挨拶
北川知克衆議院議員
左藤章衆議院議員
太田 房江衆議院議員
大阪府副知事 小河保之
5・パネルディスカッション
大阪を「健康省エネ住宅」による健康長寿・地域活性化先進都市に!
【パネラー】
東瀬幸枝 日本主婦連会長
今井敦子 大阪歯科大学 講師
岩前 篤 近畿大学 建築学部長
祖父江 友孝 大阪大学大学院医学系研究科教授
中山 邦夫 元大阪大学大学院 医学部講師
三崎信顕 大阪府住宅まちづくり部居住企画課課長
司会 上原裕之
6・閉会の挨拶
一社)健康・省エネ住宅を推進する国民会議
大阪弁護士会 元副会長 関根幹雄
【後援】 大阪府、(一社)大阪府木材連合会、大阪府地域産材活用フォーラム
お申し込みは、リンク先を参考に、FAXかメールにてお願い致します。
建物の一部を残しての解体が続いていた、K様邸。
無事に、解体工事が完了しました!
解体がはじまる前のK様邸
解体の始まる前に比べると、建物自体もどこか頼りなく感じます。
この残った部分をこれから建築する新しい建物と構造的に問題ないように、
結合していくようになります。
建物の一部を残して、解体が完了したK様邸
もちろん、残った建物にも雨や風の影響がいかないように、
十分注意して、養生を行っています。
ここから更に、残す部分と、無くす部分を分けて、徐々に新しい建物と、
融合していきます。
例えば、窓や外壁などの外に面する部分は、
殆ど新しくなる予定です。屋根に関しても新しい屋根が
この建物を覆う予定になっているので、徐々にそう言った部分は
工事の状況に合わせて、取り払っていきます。
基礎に関しては、下調べの段階で、規定の鉄筋が入っていて、
構造的には問題が無さそうなのですが、新しい建物の基礎と、
一体化することになっています。
また、内部の構造的な柱や梁に関しても、新しい建物が
古い建物の構造をフォローするような形で、建築をする予定です。
このような工事のやり方については、市役所との綿密なやり取りを経て、
工事の手法が決められて行っています。
この残った部分は、今から約8年ほど前の、増築した部分になるので、
構造的にはそこそこの強度があるのですが、別の建物と一体とすることによって、
この部分の強度だけの問題でなく、新しい部分を含んだ、建物全体のバランスを
考慮する必要が出て来ます。
そう言った事も加味して、建物全体の工事の計画を行う訳です。
ひと通りの解体が完了しました。
次は、新しく建てる部分の基礎の着工と、
その新しい基礎と、残した建物の部分の基礎とを一体化する工事に移ります。
構造的な部分の工事が終わって、雨仕舞と言う、雨が建物内に
入らないようにする工事が終わる段階になるまでは、
いつも以上に慎重に工事を進めていく必要があります。