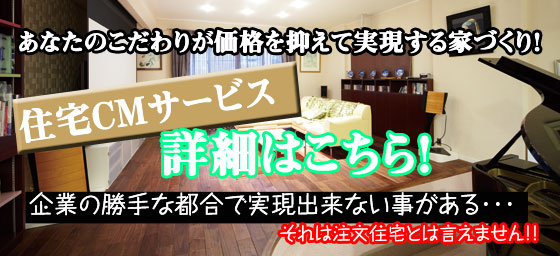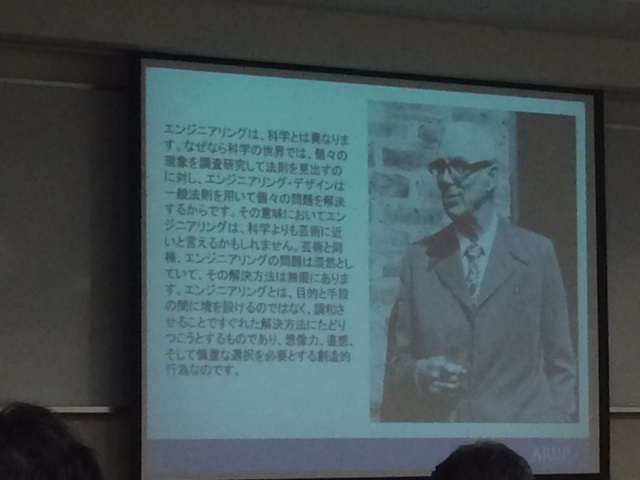家づくり関連ニュース
「スチームパンクな家が建てたい!」
そんなご希望を当初お伺いした際、
私はスチームパンクと言う言葉を初めて知りました。
建築の世界では、イギリスのヴィクトリア女王の時代(19世紀頃)に発達した、
建築様式でヴィクトリアン様式という物があります。
スチームパンクとは、その時代を背景にサイエンス・フィクションとして描かれた、
世界観のことを指すようです。
ヴィクトリア時代の中流階級より上の生活をモデルとし、
マホガニーと真鍮で作られた道具や家具などが特徴的です。
よく、映画などで出てくる、手紙にロウで封をするためのシーリングスタンプなども、
それに当てはまるそうです。
ここから発展して、機械仕掛けの時計やタイプライター、空想上の機械などが
金の装飾と歯車でカチカチ動いている。そんな世界感を表現したいと言う事でした^^
まさにヴィクトリアンなLDK
最初はスチームパンクと言う言葉自体を知らなかったので、
どんな風に表現したら良いのか難しかったのですが、
とあるブログを、ご紹介頂きそれでそのイメージを掴むことが出来ました。
そのブログがコチラです。
コチラを拝見して、やっとそのイメージが伝わってきました^^
(これを見て頂いている、皆様もそうでは無いでしょうか?)
これらをヒントに、出来上がったLDK。
壁紙から、ドアや床材、腰パネルから廻り縁(天井と壁の境にある材料)、
巾木(床と壁の境にある材料)、ドアの取っ手や、照明に至るまで、
まさにスチームパンクじゃ無いでしょうか?
寝室もかなりその雰囲気が醸しだされています。
ここから更に、家具やカーテンに至るまで、とことんスチームパンクを追求されるようです。
私が羨ましいなと思ったのは、こういったこだわりに対して、ご夫婦のご意見が一致されている事です。
大抵の場合、こう言った事をどちらかがご希望されても、なかなか家族間で意見が揃わないといった事も、
よくあります。
そういう意味で、実現が困難になることもよくあるのですが、
今回はそこの足並みがピタッと揃っていらっしゃったのが、
見ていてとても羨ましかったです!
コンセントやスイッチのプレートにもこだわられました!
上記の写真にあるように、コンセントプレート一つにしても、
とてもこだわれています。
このコンセントプレートを一つ探すにしても、
多大な労力を使われているかと思います。
そこに、大きな価値があるように思います。
壁紙一つとっても、何を選ばれるかでこの家の雰囲気が
かなり違っているはずです。
そこをピッタリとスチームパンクな雰囲気に合わせてきていることが、
この家の出来の良さを物語っていると思います。
もちろん、ドアの取っ手も金の真鍮風です!
今回使用されているドアも、かなりの労力を使って見つけ出されているドアです。
今回の雰囲気にピッタリと合わせるためです。
細部まで表現にこだわっています!
また、ここを施工した大工さんも、お施主さんのこだわりに答えようと、
新たに道具まで新調して、大工仕事をしてくれています。
まさに、大勢の家造りに対する真剣な姿勢と、
それ以上にあった、お施主さんの熱いこだわりが実現させた、
まさにスチームパンクな家が完成致しましたV
最後は皆で記念撮影!
今回も良いお引き渡しになりました!
建築は、科学でなくエンジニアリング(工学)である。
家を建てる施主にしてみれば、科学であろうが、工学であろうが、
きちんと建てさえしてくれれば、どっちでもいい事かもしれませんが、
建築学会とはそう言う事を大真面目に話し合う、建築業界において最大の権威ある学会です。
日本の建築基準法などは、この学会を通した内容をもって、
議論されることもしばしばあります。
建築学会近畿支部シンポジウム
そんな建築学会の近畿支部において、
「環境が形態を決める」-建築エンジニアリングの最前線-
と、題されたシンポジウムが開催されました。
この支部において、事務局をされている方が、
丁度、私と近畿大学で授業を一緒に受け持って頂いている先生だったと
言うこともあり、シンポジウムに誘って頂きました。
普段から、
「スマートウェルネス住宅等推進モデル事業」
と言う、住まいの断熱性と健康との関連性を全国的に調査する事業で、
お世話になっている、慶応大学の伊香賀先生も登壇され、このモデル事業の
前段階での調査結果などについてお話をされると言う事で、
私も楽しみにしていました。
沢山の先生方がお話をされたのですが、その中で私が最も面白いと感じたのは、
神戸芸術工科大学の齋木学長のお話でした。
齋木先生の今回のお話は、イギリスのロンドンの郊外にある、レッチワースと言う街の
お話でした。
イギリスが工業化の時代に入り、ロンドンの町並みがどんどん悪化していく状況を見て、
エベネザー・ハワードと言う人がロンドンの郊外にもっと人々が豊に暮らせる街を作ろうと提唱し、
実現したのが、田園都市と言われるレッチワースです。
約100年前に作られたこの街が、今もその最初に計画された予定通りの町並みを保ち、
今でも緑豊かで、永続的な人々の出入りが実現している、理想的な街のお話でした。
日本では、無秩序な都市開発が隅々まで行き渡っていってしまったために、
外国人が日本の町並みを見て、「汚い町並み」と揶揄されるようになってしまいました。
悔しいのは、まだ明治維新前に鎖国状態であった日本を見た、イギリス人やアメリカ人は、
息を飲むほど美しい国だったと、言っていた史実があると言う事です。
田園都市であるレッチワースの特徴は、やはり緑が豊であること。
豊かな緑が心のゆとりや生活の安心感など、我々日本人がどこか置いてきてしまったであろう、
「生活の質」を与えてくれている。そんな気がしてなりませんでした。
今の日本の多くの土地開発は、山を切り裂き、限られた土地をなるべく沢山区切り、
そこになるべく多くの建物を建てて、「儲けること」が重視されています。
それに引き換え、レッチワースは土地の所有者の利益より、町並みを醸成し、
人々の暮らしの質が高くなることによって、その街全体の価値(金銭的にも価値が上がる)が上がって、
居住者全てが恩恵を受けるそんな街を100年も前に構想していたのです。
私はこの話を聞いて、悔しい思いがしてならなかったです。
我が子が道を歩く時、危険な自転車や自動車に鉢合わせて事故が起きないかばかりを
気にしなければ、歩くことすら出来ないこの町並み。
歩いても歩いてもまだまだ遠い公園。
我が子は緑が好きなようで、草を見つけては立ち止まって、
しゃがんでその様子を眺めています。
彼にもっと偉大な自然をすんなり感じさせてやる方法は、
他に無かったのでしょうか?(そう言う場所に引っ越せばいい?)
今、日本では空き家の問題が取り沙汰されています。
しかし、一方で今まで人が住んでいなかったような場所で、
山を切り裂き、自然を破壊して、特定の人間の儲けのために、
宅地が作られ続けています。
何かおかしく無いでしょうか?
本当に日本人は、豊になったのでしょうか?
そんなことを考えさせられるシンポジウムでした。