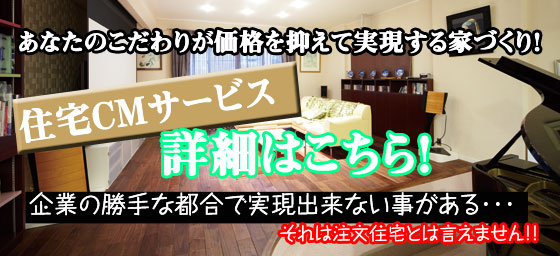家づくり関連ニュース
シルバーウィーク中に、多くの面談が行われました!
すっかり定着したシルバーウィーク。
この期間を利用して、家づくりを加速されるご家族も多いようです。
住宅CMサービスご利用中の方々も面談を行われる方が多数ありました。
工務店さんと面談中のT様
面談では、それぞれの工務店さんが得意としている家づくりについてや、
家づくりに対する姿勢、思い入れなどをご確認頂いています。
それぞれの工務店さんにはカラーが有り、自分たちの思いを実現するのに、
どんなスタイルの工務店さんが良いのかを見分けるための場としています。
とは言っても、
「そもそも、工務店さんには一体どんなスタイルの工務店さんがあるのか?」
と、言う事を見分けるのは、一般の方には非常に難しいと思います。
ですので、我々のような経験のあるプロが同伴することで、
それぞれの工務店さんが持っているスタイルを肌で体感して貰い、
その方向性や姿勢の違いを感じて貰う事がとても大切です。
工務店さんと面談中のT様
一回の面談だけで、分かる事も多いでしょうが、もちろん分からない事も沢山あると思います。
ですので、この一回限りのチャンスで決めなくてはならないと言う事は全くありません。
その場で感じれなかった事を再度確認するために会って貰うことも可能ですし、
その他の方向性や実力を確認するために、過去に建てた建物や、
過去に建てた経験のあるOBユーザーさんに会ってもらう事もしています。
面談とは、その最初の入口と言う位置づけで、これからお互いをよく知っていくための
プロセスの始まりでもあります。
そして、お互いがもっとよく知りたいとなった相手に対して、
より深く知り合って貰う機会を設ける。
それにより、相互理解が深まれば、家づくりを一緒に行って貰うと言う事を行っています。
工務店さんと面談中のS様
工務店さんの中にも、真剣な家づくりを行っている良い工務店さんが沢山あります。
そんな工務店さんは、一体どんな工務店さんなのか?
そう言った工務店さんが、どんな具合に真剣な付き合いをしてくれるのか?
そう言った点を知って貰う事がとても重要です。
納得のいく家づくりの第一歩として、面談と言うキッカケを大いに利用して貰い、
家づくりを実現するためのパートナーとして、最適な相手は誰なのかを検討して貰っています。
もちろん、そのために要する時間に制限は設けていません。
企業の勝手な都合のために、
「明日までに契約して下さい!」
と、言った事は一切していません。
それは、人生で一番お金が掛かり、下手をすると人生の多くの時間で払い続けなければならない、
借金を背負うお施主さんに対して、あんまりだと私自身が感じて、思っているからです。
人生の豊かさ、ライフスタイルの多様性は、人に強要された「契約」によって、
実現することは無いように感じています。
ご自身が納得して、こことなら一緒に家づくりが出来ると感じて、
最高の自分のオリジナルを実現した注文住宅であるからこそ、
愛着が湧き、その後の生活も充実したものになるのでは無いでしょうか?
過去の日本人は、家にボロが出て来たとか、何かが壊れたとか、
必要に迫られた時にしかリフォームをしなかったそうです。
これに対して、欧米では「生活をより良くするため」にリフォームをするようです。
これからの日本人も、生活に対して、このような意識を持つべきです。
「より良い生活をするため」
に、新しい家を建てるべきだと思いますし、そのための納得した住宅であるべきです。
それを実現する「みちしるべ」として、これからも家づくりを支えて行くことが、我々の使命であり、
面談とはそう言う場でありたいと思っています。
生憎の台風となってしまったこの日、スマートウェルネス住宅の普及啓発活動の一環として、
大阪におけるシンポジウムが開催されました!
多くの建築関係者が詰めかけ、100名を超える参加者となりました。
シンポジウムの司会進行役を務める太田
スマートウェルネス住宅とは、省エネで且つ健康維持や増進につながる住宅の事を指します。
今回のシンポジウムでは、
・スマートウェルネス事業の現状と今後、
・住まいと健康との関連性
・スマートウェルネス住宅が大阪と言う地において、どのように普及されるべきか。
・実際のスマートウェルネス住宅へのリフォーム事例報告
と、言った流れで開催されました。
スマートウェルネス住宅推進事業の現状について話をする上原理事
まず、最初に今回の主催者である、(一社)健康省エネ住宅を推進する国民会議の上原理事より、
スマートウェルネス住宅等推進活動に関する現状と、今後の展望についてのお話がありました。
そこでは、新たに政府の各省庁や、医師会・看護師会などと連携して、
スマートウェルネス住宅の在り方を検討する委員会が発足した旨の報告がありました。
基調講演に登壇頂いた、山口県立大学の江里理事長
山口県立大学の江里健輔先生(山口県立総合医療センター元院長)の基調講演では、
住まいが健康に与える影響についてのお話が行われました。
特に、「心臓疾患」に対する影響は、温度差による要因も大きく、
住まいにおいても、温度環境を整備することの重要性をお話頂きました。
同時に今の医療制度が抱える問題点のお話にも至り、とても貴重なお話を聞かせて頂きました。
パネル・ディスカッションの様子
後半には、おおさか健康省エネ住宅推進協議会の事務局長でもあり、
NPO法人地球の会の事務局長でもある、佐藤善秀氏が進行役となり、
このスマートウェルネス住宅が大阪においてどのような形で、どのように普及されるべきかつにての、
パネルディスカッションが行われました。
今回のスマートウェルネス住宅は、住宅単体だけの問題に限らず、
地域全体として、高齢者に対する支援を行なうと言う考え方に基づいた、
「地域包括ケアシステム」とも、深い関連性があります。
そこで、看護師である三輪五月氏による、地域包括ケアシステムにおける、
住まい環境の重要性についてのお話がありました。
より自立した高齢者の生活を実現すると言う観点からも、
寒い自宅で過ごすよりも、温度環境の整った住まいで過ごせるようにすることが、
今後の社会には必要となるようです。
また、COOPでおなじみの日本生活協同組合連合会(生協)の
品質保証本部安全政策推進部長である、鬼武一夫氏によると、
高い品質のものを提供する事が目的である生協は、
スマートウェルネス住宅が真に消費者にとって、重要なものであると言う位置づけられる
ものとして、普及啓発の協力が可能である旨のお話を頂きました。
また、大阪府まちづくり部都市居住課の三崎課長からも、
大阪におけるスマートウェルネス住宅の在り方について、
今後も継続して議論すべきである旨のお話があり、今後も引き続きその位置づけについて、
話し合いが行われる予定です。
また近畿大学の岩前教授からは、現在、スマートウェルネス住宅等推進事業の一環として行われている、
「住生活空間の省エネルギー化による居住者の健康状況の変化等に関する調査事業」が、
もたらしうる意味や、大阪における調査の重要性などについてのお話がありました。
また、パネル・ディスカッションにおける江里健輔先生のお話では、お医者さんによる、
普及啓発が理想的であると言う見解の一方、お医者さんにその明確なインセンティブがない限り、
なかなか医者の立場としての普及啓発を行なうことは難しいのでは無いかというご意見もありました。
総じて、国が推進しているこのスマートウェルネス住宅が如何に重要であるのかと言う事を
多くの方に理解して貰う必要があり、概ねその啓発に向けた方向性は関係各所で同じであると言うことと、
国の明確な基準とするためには、エビデンス(調査結果)が今後の方向性を位置づけるであろうことが確認されました。