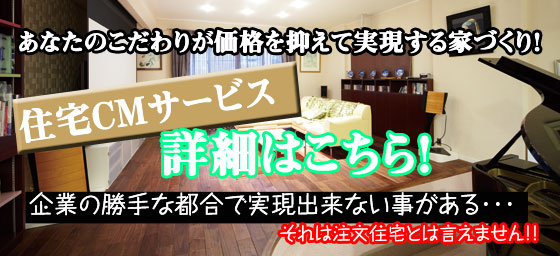家づくり関連ニュース
とてもよい天気に恵まれたこの日、午前中は吹田市で地鎮祭が行われました!
現在、石川県に在住のK様。この日は朝から車で石川県からお越し頂き、
地鎮祭を行いました!
最近の雨の多さに天気を心配していたのですが、
この日はいい天気に恵まれ、気持ちの良い日でした!
K様は、この土地をご自身で探されて購入されたのですが、
土地を探される際も、地形図を見て、昔の土地の様子を調べたり、
建築するに辺り、問題が無いかどうかなどを事前にしっかり調べて、
ご購入されています。(もちろん、私も事前にチェックしています。)
しかし、これからの工事で土地の神に地を鎮めて貰い、
より良い工事が出来るように願うことは、関係者の気を引き締める意味でも、
重要なことなのでしょう。
最近聞いた話では、関東の方では、今では地鎮祭すらも行うことが無いそうです。
もちろん、それ自体が良いとか、悪いとか言う話ではありませんが、
「よい建築を願う」
と、言う感情表現をする場として、地鎮祭は恰好の場のように思います。
地鎮祭をしない場合も、何らかの形でそう言った
「思いを改に伝える」
場面があると、より良いのかもしれません。
(もちろん、それまでの打ち合わせで散々伝えているかもしれませんが、
改めてと言う意味で。)
お天気に恵まれた、地鎮祭!
地鎮祭で必ずと言って良いほど行われる地鎮の儀、
今回も抜かり無く行われました!
そして、実際にこの下の写真にある鎮め物は、
基礎工事が始まるその時に、土地に埋めて鎮めて置いておきます。
そのようにすることで、「地を鎮ずめる」のです。
地鎮の儀にて、鎮め物
地鎮祭の後、昼食がてらに打ち合わせを行い、
そのままの足で今度は、岩出市で行われている上棟現場へと向かいました。
雨が続いて、こちらも天気が心配されましたが、
和歌山県においても天気に恵まれ、順調に工事が行われていました。
しかし、翌日には再度、雨の予報になっていましたので、
養生をして、雨を防ぐ事が出来るように、なんとか屋根まで作ってしまおうと言う事で、
棟が上がり、そのまま屋根の骨組みを作り、そこに瓦などの屋根材の下地になる、
野地合板と呼ばれる、合板を施工し、防水用のシートを貼り付けるところまで、
工事が行われることになっていました。
上棟の様子
現在の屋根では、主に「アスファルトルーフィング」と呼ばれるシートを、合板の上に貼り付けることで、
防水することが多いです。
昔は、バラ板と呼ばれた、板を屋根の骨組みに敷いて、その上に藁と混ぜた土を載せ、
更にその上に瓦を載せるといった方法で、屋根を作っていました。
しかし、その方法は屋根が極端に重くなるので、近年では防水には、
薄くて軽い、シートを利用します。
この日は、そのシートを貼るところまでを工事目標としていました。
家の四隅に酒と塩と米を撒く
ここでも、簡単ではありますが上棟式を行うことになっていたので、
夕方までに目標の工事を終わらせる必要があります。
大工さんの頑張りもあり、なんとか夕方までには、目標の工事を終えました。
上棟式は、これから家を建てるリーダーとも言うべき、
大工さん(棟梁)への労いの意味も込めて行います。
一昔前までは、上棟式と称して、大工さんにご飯やお酒を振る舞い、
盛大に宴会をすることが通常でした。
そして、地域によっては村の人々を集めて、出来上がった家の屋根から、
餅を撒いて、村の人々と一緒に盛大に盛り上がることもありました。
しかし、現代ではそう言った事がかなり簡素化されて、
こちらも、上棟式をやらない場合も多いようです。
大工さんたちは車で来ている事が多いので、
酒を振る舞うことは出来ませんので、当然と言えば当然かもしれませんが、
こちらも、地鎮祭同様、節目に改めて、建築への思いを伝える、
丁度良い機会になると思います。
そうして、人と人との繋がりで出来上がっていくのが、家づくりです。
どんな家でも、何かしら人の手は加えられます。
そう言った、家づくりならではの側面は、とても良い文化だと個人的には思います。
形式的なものはいずれ、忘れ去られる日が来るかもしれませんが、
その意味はいつまでも残って貰いたいものです。
スマートウェルネスハウスを普及させるための事業の一環として、
全国の普及啓発活動に協力してくれている工務店さんのサミットが開催されました。
私はその中で、講演をさせて頂きました^^

工務店サミットの様子
最初に、一般社団法人健康省エネ住宅を促進する国民会議の上原理事がお話に立たれました。
上原先生は、本業は歯医者でありながら、90年代にご自身が施主となり建てられた自宅にて、
ご家族が患われた症状の原因を突き止めようと、最初の活動を始められました。
後に上原先生が名付けられた、「シックハウス症候群」は、全国的な問題となり、
やがて建築基準法が改正されました。
その後、再度建てられた住宅において、今度は室内の温熱環境が原因で、
また、新たな症状が発症しました。再び上原先生が中心となり発足したのが、
「健康・省エネ住宅を促進する国民会議」です。
今回、この国民会議の活動としては、国が主導で行っている、スマートウェルネス住宅等推進モデル事業にて、
室内の温熱環境が如何に健康に影響を与えるのかを調べるための疫学調査の協力を行っています。
そして、この活動に賛同する工務店さんが、今回全国から集まってきて、
工務店サミットなるものを開催することになりました。
このような経緯で集まった方々の数は、ゆうに150名を超える数だったようです。
その方々の前で、今後、集まった工務店さん達の有益な情報となるように、
私が依頼されて、講演を行いました。
今回の調査においては、断熱リフォーム前後の健康状態を比較することによって、
それが人体にどれほど影響を与えるものなのかを調査しています。
ですから、断熱リフォームで屋内の温度状況が、ある程度改善される事が
比較調査では重要になります。
これらの点を踏まえて、どのようなリフォーム提案を行なうことが、
今回の調査に対して、有益な結果に繋げられるのかと言った観点から、
なるべく、断熱効果を最大化して、元々住んでいた家の温度の状況より、
遥かに安定して、温度状況が変わるように、一旦はお施主さんに提案する必要があります。
もちろん、疫学調査なので温度環境が変わった結果、
健康状態に改善が見られたのか、それとも全く見られなかったのかは、
今のところ確定的な事は言えません。
しかしまずは、温度環境がハッキリと変わったと分かる程度まで、
断熱リフォームを行なうことが重要です。
今回のスマートウェルネス住宅など推進事業では、この断熱リフォームに対して、
補助金が交付されます。掛かった費用の半分か又は最高120万円がその補助額です。
この補助金を貰うことが目的になってしまうと、大した断熱リフォームで無くても、
補助金が貰えてしまうことになります。
補助金を貰うためには、今回の疫学調査にお施主さんが協力することが必須なのですが、
断熱リフォームに対する基準が低く、場合によっては劇的な温度環境の改善が見られない場合があるのです。
そう言った事を防ぐためにはどうしたら良いかと言った、根本的な基準のお話をさせて頂きました。
リフォームですので出来ることは限られていますが、その中でも出来る限りの断熱リフォームを施し、
温度環境の改善を行なう提案をまず行なうことが重要というお話をさせて頂きました。
当然、予算は限られているので、実際には出来るリフォームは異なることがあるとは思いますが。