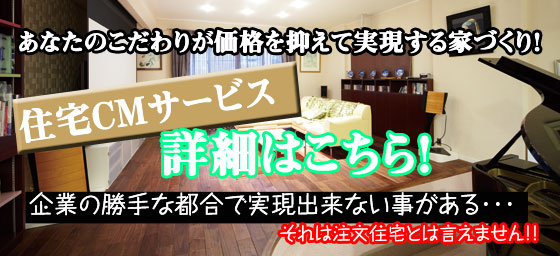家づくり関連ニュース
近畿大学さんの生物理工学部は、和歌山県の紀の川市にあります。
自然に囲まれたとてものどかなこの場所で、依頼されていた特別講演をさせて頂きました。
大学院生を対象としたこの講演ですが、定期的に行っていらっしゃるそうです。
様々な社会人から話を聞いて、今後に役立てると言うコンセプトの講義のようですが、
登壇される他の方々のお名前を拝見すると、同じ講演の形式でお話させて頂くのが、
とても光栄な錚々たる方々ばかりでした^^;

近畿大学生物理工学部の校舎
そんな中、まだまだ人間としても企業人としても発展途上である私が、
どんなお話しようかとかなり悩んだのですが、
私がどこか大きな企業の創業者のような成功話を出来るわけもなく、
こんなことをしたら、大きな成功が出来ました。
と、言えるような話も出来ないと思い、最終的には
「話せることは自分の経験しかない!!」
と、私が今に至るまで、如何に失敗を繰り返してきたかという話を中心に、
その失敗から何を得、どのように今に至っているのか。
と、言った話をさせて頂きました。
改めて今までの経験を振り返ってみると、殆ど失敗や挫折、苦い経験を経てここまで来ているように感じます。
話は、阪神大震災にて実家が倒壊し、祖父が亡くなったところから始めさせて頂きました。
そこで、何を感じ、どんな行動をしたのか。
また、大学に入ってから何を失敗し、そこで何を学んだのか。
今思えば、何をもっとしておくべきだったのか。
就職先に選んだ会社は、どのような思いで選んだのか。
そして、就職してからどんな失敗や経験をしたのか。
そこで得たものは何だったのか。
丁度、この講義に参加してくれた学生たちと同じ頃の
自分の話をさせて貰いました。
そして更に、今こうして独立し、仕事というものをどう捉えているか。
そして、仕事上は絶対について回る、お金というものについて、
自分はどう考えているのかと言ったことをお話させて頂きました。
私は、
「お金は信頼の対価」
と、考えています。
なので、その順番が逆になるような事は、絶対に避けるべきと考えています。
お客さんに信頼して貰って、始めて何かを提供し、その結果としてお金が入ってくる。
なので、お金が目的となってしまっては本末転倒と考えています。
そして、仕事とは「自分に出来ない(無い)何かを、相手を信頼して任せること」だと思っています。
なので、何かしらの人の役に立たなければそれは、仕事とは呼べないと思っています。
それが、誰の役に立つのかは立場によって変わるのだと思いますが、
少なくとも、自分に返ってくるのはその後だと思っています。
やりたい仕事、自分にあった仕事を探すのもとても大切なことだと思いますが、
それだけでは、仕事としては成り立たないと思います。
そう言った、普段の心掛けのようなお話についても話をさせて頂きました。
聞いてくれた学生達から、熱心な質問がいくつか飛んできました。
私が建築の人間なので、事前に質問を考えて来てくれていたように感じる学生もいました^^
この講演を通して、もし何か少しでも今の足しになったのであれば、
本望だと思っています。
今回の講演に呼んで頂けたことをとても感謝しています!!
熊取町にて新たな工事が始まりました!
この日は、基礎の捨てコンクリートの施工の様子を確認しにやってきました。
基礎の捨てコンクリートとは、基礎の底面を平滑・水平にするために行う、
基礎を綺麗に施工するための事前準備として施工するコンクリートの事です。
この捨てコンクリートを行うことで、基礎の高さをより正確にして施工することが可能となります。
下の写真では、まさに捨てコンクリートの施工真っ最中の様子です。
基礎の捨てコンクリート施工中!
大きなホースを背負っているのが、ポンプ車から送られてくるコンクリートを必要な箇所に
流し込む施工を行う職人さんです。
そして、もうひとりが流されてきたコンクリートを平滑にかつ、高さを予定の高さに保つために、
施工を行う職人さんです。
高さを確認するための機械
そして、この機器がレーザーレベルと呼ばれる機械で、この機械を水平に据えることで、
レーザーが水平に放出されます。
このレーザーを先程の職人さんが確認しながら、高さの調整を行うわけです。
建物が歪んだりしないか、真っ直ぐに建てることができるかは、
この時点からの微妙な調整から既に始まっています。
まさに、基礎が大事と言うのは、この点も往々にして含まれています!
コンクリート車からピンプ車へ!
こちらは、コンクリートミキサー車と、ポンプ車がコンクリートの受け渡しを行っている部分です。
コンクリートミキサー車(コンクリート車)は、コンクリートを運ぶことが主な仕事となっています。
コンクリートは、プラントと言う場所でコンクリートの原材料を混ぜ合わせて作ります。
出来上がったコンクリートには、賞味期限があり、これがかなり短い時間となっています。
(JISと言う規格では、練り混ぜてから現場に到着するまで90分となっていますが、
建築学会と言うところが規定している内容では、練り混ぜてから施工が終わるまでを、
25℃以上の気温がある場合で、90分としています。25℃未満なら120分)
ですので、施工時間にはあまり余裕があるわけではありません。
ある意味、時間との戦いとも言えます。
我々が確認する際は、工場からの出荷伝票を参考にその時間を確認したりする訳です。
(コンクリートはすぐに固まってしまいますので。)
ですので、運ぶ道中にコンクリートが固まったりしないように、コンクリートミキサー車によって、
かき混ぜながら運んでくるわけです。
そして、運び込まれたコンクリートは、こんどは現場に打設(コンクリートを流し込むこと)するために、
ポンプ車に入れ替えられます。これが上の写真の瞬間です。
ポンプ車には、強力な圧力がかかっていて、その圧力によってポンプからコンクリートを
押し出しているのです。ですので、ある程度屈強な体をした職人さんで無ければ、
なかなかホースを上手いことコントロールすることができません。
地味に見えますが、結構大変な仕事なわけです。
(最近は季節が良いですが、これが夏だと炎天下で大変なのです。)
本の小一時間程度で、家全体の捨てコンクリート施工が終わりました。
ここから、基礎の鉄筋工事が始まっていきます!