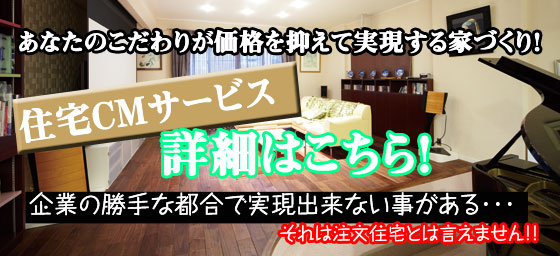家づくり関連ニュース
1年の月日が流れるのも早いものです。
昨年、お引き渡しした住宅が、完成1年を過ぎ、
1年目点検が行われると言う事で、工務店さんがK様邸を訪問するタイミングで、
新年会をしようと言う事になったようで、私も新年会にお招き頂きました。
私も1年経った家に招いて頂くので、
色々な住まい状況について、お話が伺えると楽しみにしておりました。
1年前に完成した当時のK様邸。
久しぶりにお伺いしたK様邸。
一番最初に元気にお出迎えして頂いたのは、息子さんでした^^
どうやらとても楽しみにして貰っていたようです。
早速、1年点検と言う事で、家の周りからチェック。
サイディングのコーキングの割れや、基礎に異変が無いかなどを、
目視で確認していきます。
雨水の排水なども詰まっている様子もなく、
順調なようです。
屋内からは、床下の点検や建具の開閉確認など。
寝室の開きドアが、少し擦れて、枠に当たるようになったとの事。
ドアの丁番は、使っている内にどうしても少しづつずれて来ます。
今の建具の丁番は、その辺りが直ぐに調整出来るようになっていて、
ネジを回して調整すれば、直ぐに元通りになりました。
更には、換気扇が詰まっていないかなどを、換気の給気・排気口の風量を
元に確認。フィルターが目詰りしていて、風量が落ちていました。
直ぐに水洗いしてもらい、こちらも問題なく修正。
1年経って、改めて効果の程が確認できたのが、外壁。
親水性の塗膜のある外壁なので、雨だれなどの汚れが
殆ど目立ちません。返って、シャッターの笠になっている部分のほうが、
雨だれが目立つほどです。(面積が小さいので、良く見ないと分かりません。)
親水効果は、結構効いているようです。
更には、エアコンの運転の様子を伺うと、いつもファンが動いているとの事。
どうやら、購入されたエアコンの初期設定では、温度が目標の温度になると、
送風運転として、ファンが回ったままになるようでした。
ですので、リモコンから、エアコンが目標の温度に達したら、ファンが止まるように
設定しなおし。これで電気代ももう少し節約出来ると思います。
この冬場、この日もそうでしたがK様邸では、常にエアコンを18℃設定にされているそうです。
確かに、それでも寒いと感じるような事はなく、むしろ人が集まって食事をしていると、
段々、ホクホクしてくる感じすらありました。
やはり、断熱性能がよくなると、そもそもの暖房の設定温度すら、かなり低くしていても
大丈夫なようです^^
点検を終え、工務店の社長さんも後から訪ねて来られたところで、
新年会を催して頂きました^^
新年会では、今まであまりお話していなかったような、私のプライベートな
お話までさせて貰い、うちの場合はこうだとか、あぁだとか、色々なお話が聞けました!
非常に居心地が良いので、甘えているといつまでも居てしまいそうになってしまいます。
心も体も温まる、楽しい新年会となりました!!
暖かいご家庭の様子が伺えて、仕事冥利に尽きる、良い一日でした。
K様、有難う御座いました!
新年から、おめでたいことに門真市で建築予定のK様邸の 地鎮祭が行われました。
それまでの雨が嘘だったかのように、
地鎮祭の時間に合わせて、晴れ間が見えて来ました。
地鎮祭のメインの一つといえば、地鎮の義。
地鎮の儀とは、事前に祭壇向かって左横に準備した、
砂山に、鎮め物を納める儀式。
実際には、基礎工事をする際にこの「鎮め物」を納めるのですが、
地鎮祭では、地鎮の儀で鎮め物を納める儀式を行います。
地鎮の義一つとっても、最初に設計者による「刈り初め(かりそめ)」と言って、
事前に用意した砂山に、草を一本指しておいて、それを設計者が刈り取る儀式を
行う場合と、行わない場合があります。
今回は、刈り初めは行わずに地鎮の儀が行われました。
順を追って見ていくと、
地鎮の儀:まずは施主さんが砂山を鍬で3回起こします。
写真のような砂山を、施主さんであるK様が、3回鍬で砂山を起こします。
鎮め物を鎮めるための、穴を空ける感じです。
慣れていない方が多いので、実際には掛け声なしの場合も多いのですが、
本当は、鍬で起こすと同時に、「エイ!エイ!エイ!」と、大きな声で
掛け声をかけると、それらしくなります^^
大概は、そんなものと知らずにためらってしまいますが。
次に神主さんが「鎮め物」を納める。
施主さんが空けた、鎮め物を鎮めるスペースに、今度は神主さんが鎮めものを納めます。
神主さんにより様々ですが、鎮め物を納める際に、勢い良く、砂山を崩して納める方もいます。
今回の神主さんは、特に一般的な納め方だったと思います。
納められた鎮め物はこんな感じ。
地鎮の儀では、写真のように鎮め物が納められます。
この鎮め物の中身は、
「人型、盾、矛、小刀、長刀子、鏡、水玉 の七つ」
と、言われていて、それらを絵に施した器が入っているそうです。
開けたらご利益が無くなるそうなので、実際には開けていませんが・・・
地鎮祭が終わると、この鎮め物は一旦取り出し、
実際に工事が始まるまでの間、施工者によって保管されます。
最後に工務店さんが鋤で3回砂を均します。
最後に、施工者である工務店さんが鋤で砂を3回均し、
納めた鎮め物に砂がかぶさって行きます。
流石に工務店さんは慣れているので、
大きな声で「エイ!エイ!エイ!」の掛け声^^
地鎮祭らしい感じがします。
その後も粛々と祭りが進行し、無事に地鎮祭が終了。
一時持っていた雨も、地鎮祭が終わってしばらくすると、
降り出しました。
さて、工務店さんが保管する鎮め物ですが、
実際に工事が始まると、基礎工事を行う時に、
今度は本当にこの鎮め物を、基礎の中に納めてしまいます。
土の中で、地を鎮め、工事の無事と、その後の末永い暮らしを
支えてくれているのでしょう^^