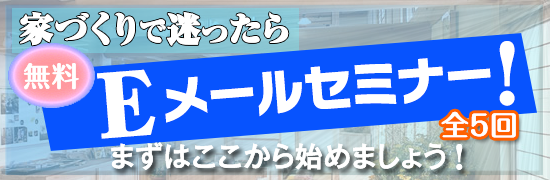◆ ツーバイフォーの歴史
ツーバーフォー工法は俗称で、正式には「枠組み壁工法」と呼びます。
ツーバイフォー工法は、アメリカの開拓時代に考案された工法です。
この時代は、誰もが簡単に家を建てられる必要があったため、決まった大きさの材料を組み合わせて、
釘で留めるだけのこのツーバイフォー工法が普及したのです。
<スポンサーリンク>
現在の1階と2階を構造的に切り離した工法に落ち着いたのもこの時期です。
また、この時期に金物も併用した工法となっていきました。
日本では、明治頃から北海道にこの工法が伝わり、住宅としては明治末期から輸入され始めました。
今のツーバイフォー工法と呼ばれ始めたのは、技術基準が定められた昭和49年頃からです。
つまり、ツーバイフォー工法の歴史は非常に浅いのです。
◆ ツーバイフォーの構造の特徴
ツーバイフォー工法は、2インチ×4インチの大きさの材料を基準として、
規格の大きさ数種類の組み合わせで、家の骨組みを構成します。
材料の種類は以下です。
・204(38mm×89mm) ツーバイフォー
・206(38mm×140mm) ツーバイシックス
・208(38mm×184mm) ツーバイエイト
・210(38mm×235mm) ツーバイテン
・212(38mm×286mm) ツーバートゥエルブ
・404(89mm×89mm) フォーバイフォー
の6種類と構造用合板だけであり
これらの大きさが世界共通となっているため、材料の大幅なコストダウンが出来ます。
また、基本的には材料と材料を釘で留めて構成するために、比較的作業者(大工)の力量に左右されにくい
工法となっています。
木を使う工法なので、木造住宅ではありますが、一般的な木造軸組み工法とは違って柱で家を支えるわけではなく、主に壁で支える工法です。
右図のように、ツーバイフォーは壁を合板で覆ってしまう工法なので、比較的「揺れにくい」工法と言えます。
<スポンサーリンク>
<スポンサードリンク>
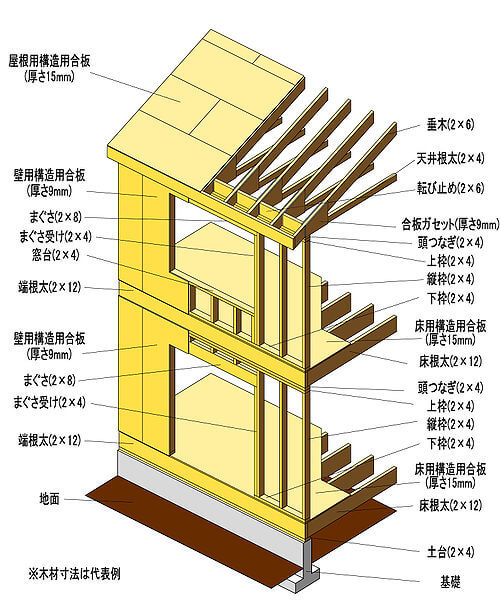
◆ ツーバイフォーの設計上の特徴
ツーバイフォー工法は、安全上の理由から法律で定められた設計上の
制約が多いため、木造軸組み工法より、間取りなどが制約されやすい
工法です。
◆ ツーバイフォーの施工上の特徴
ツーバイフォーは主に釘と金物で材料と留めつける工法です。
これらの釘は全て使用する大きさや間隔などが決められています。
ですので、比較的腕の良し悪しの差が出にくい工法です。
また、大きな特徴の一つとして構造材を組み上げるのに
日数が掛かります。
この間に雨が降ると、乾くまでに時間がかかりトラブルになる
場合がよくあります。
ミサワホームやエスバイエルなど大手ハウスメーカーでは、
この欠点を克服するために独自に開発した工法を
採用してるところもあります。
◆ ツーバイフォーの欠点
この内容は、ツーバイフォーの欠点をかなりリアルに表現しています。
既に、ツーバイフォーで建てている方、ツーバイフォーに決めている方は
ご覧にならないことをお勧めします。
→ツーバイフォーの欠点
◆ ツーバイフォーで建てることができるハウスメーカー
<スポンサードリンク>