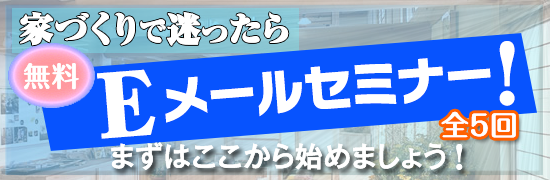|
On-site flow
契約前までに 現地調査 敷地調査 地盤調査 などの調査を行い、図面や仕様の確認を行います。 その後、金額の確認を行い合意すれば建築主(家を建てる方)と請負者(工務店やハウスメーカーなど)契約を結ぶのですが、その後工事はどのように進んでいくのでしょう。 ここでは、工事の流れと簡単なチェックポイントをまとめました。 |
|
目 次 |
工事の流れ
工事の流れを工程表で確認してみましょう。
<スポンサードリンク>
| 工事期間 | 1か月 | 2カ月 | 3カ月 | 4か月 | 5か月 | 6カ月 |
| a.解体工事 | 解体 | |||||
| b.仮設工事 | 搬入・地縄 | 足場組立 | 足場解体 | |||
| c.基礎工事 | 根切 型枠 コンクリート打設 |
|||||
| d.木工事 | プレカット | 上棟 屋根、外壁、 内装下地 |
床張 内装ボード張 |
仕上 | ||
| e.屋根工事 | 屋根葺 板金 |
|||||
| f.建具工事 | 外窓取付 | 室内扉取付 | ||||
| g.外壁工事 | 外壁張 | 樋 | ||||
| h.塗装工事 | 外壁塗装 | |||||
| i.内装工事 | 造作家具 | 左官工事 クロス貼 |
||||
| j.断熱工事 | 外壁 | 天井・床 | ||||
| k.電気工事 | 配線 換気配管 |
機器設置 | ||||
| l.給排水工事 | 立ち上り配管 | 内部配管 | 外部配管 | 機器設置 | ||
| m.ガス工事 | 立ち上り配管 | 内部配管 | 外部配管 | 機器設置 | ||
| n.外構工事 | 玄関ポーチ | 門扉 車庫 造園 |
||||
| 検査 | 確認申請 | 中間検査 | 完了検査 |
モデルとした建物の例
<スポンサードリンク>
※ 木造軸組み工法2階建て 約35坪
※ 充填断熱工法
※ 外装:サイディング 内装:クロス、聚楽塗り壁
各工事の内容は、次の項で紹介していますので、確認してください。
ここで紹介したのは一例で、工事の種類によって、工事の内容や工程は変わってきますが、おおむねこのような工事内容と勧め方になっています。
木造軸組み工法の場合は、目安として、上棟から家の床面積が10坪で1か月程度を見込んでいると完成までの所要時間が分かります。
たとえば、50坪の家の場合は、上棟から5カ月ほどで引き渡しを受けられるといった具合です。
なお、工場から部材を入れて、ほとんど加工が必要なく取り付けられるような場合と、現場で加工しながら組み上げていくような場合では所要時間が大きく変わります。
また、手間を加えることで住んだ後の不具合が少なくなったり、一人の棟梁が現場を担当する方が責任の所在をはっきりしやすいといったことがあるのですが、工期が短いとそういった配慮が難しくなる場合があります。
仮住まいなどの出費などがあるため、できる限り工期は短い方がいいといった希望があるとは思いますが、無理やり工期を短くするのではなく、少し余裕を持った計画を建てるようにしましょう。
<スポンサードリンク>
工事内容について
工事の流れで紹介しましたが、ここでは、それぞれの工事の内容を確認しましょう。
a.解体工事 (必要な場合のみ)
家を建てる土地に既存の家がある場合には、その家を解体する工事が必要になります。
今は、産業廃棄物の処理は、細かな分別の方法が決められており、昔のように一気に壊して出てきた廃棄物をまとめて捨てるということは出来なくなっています。
b.仮設工事
工事に必要な電気やトイレ、足場などの設置を行います。
近隣に建材の破片が飛んで迷惑がかかる部分には、養生用の飛散防止シート(メッシュシート)が設置されているか必ず確認しましょう。
c.基礎工事
<スポンサードリンク>
遣り方・根切・型枠工事・コンクリート打設などが基礎工事です。
・ 遣り方
家の位置や基礎の高さなどを決めるためのもので、これを基準に今後の工事を進めていきます。
・ 根切り
基礎の底面は地盤面よりも下になるため、地面の掘り起こしが必要です。
その作業を根切りと言います。
・ 地業
地盤に応じて杭を施工したり、基礎を施工する前の工事になります。
建物の高さにも影響する大切な工事です。
基礎の種類によっては、土を盛る必要もありますので、しっかりと転圧(突き固め)がされているかチェックが必要です。
・ 防湿シート施工
地面からの湿気が基礎の中に上がってこないように、防湿シートを施工します。
採石の上に施工する場合もあるので、十分な厚み(0.2mm以上)があるか確認しましょう。
やぶれていたり裂けている場合には、その部分を補修するよう依頼して下さい。
<スポンサードリンク>
・ 捨てコンクリート施工
次の配筋工事をする際の位置決めや基礎の水平を決める工事です。
このコンクリートは家の強さに直接関係するものではありませんが、家が傾きなく建てられるために、重要な意味があります。
・ 配筋工事
基礎の鉄筋を組んでいく工事です。
家の寿命や強度に大きく関係する工事になりますので、とても重要です。
チェックポイントで確認してください。
・ 型枠工事
基礎を流し込むための堰を作るための工事です。
設計図書通りの厚みが確保されているかなどはここで確認してください。
・ コンクリート打設
基礎のコンクリート打設は、
基礎の底板(スラブ) → 立ち上がり の場合と
スラブと立ち上がりを一体打つ「一体打ち」があります。
一体打ちの方が継ぎ目の隙間が生じにくく耐久性が高いとされています。
また、コンクリートは、いろんな試験すべてで合格したコンクリートか設計や計画と相違がないかの受け入れ検査をしているかを確認するといいでしょう。
立ち上がりは型枠の幅で厚みを確認できますが、スラブは、ロッドと呼ばれる大きな物差しで厚みの確認を依頼してください。
<スポンサードリンク>
d.木工事
・ 土台敷き
コンクリートの養生期間が過ぎたら、基礎の立ち上がりに土台を敷く工事に進みます。
土台は、アンカーボルトなどでしっかりと緊結されているかどうかを確認してください。
このアンカーボルトは適切な位置がありますし、水平が取れているかなどチェックポイントをしっかり確認してください。
・ 建方 ~ 上棟
いよいよ家のかたちが少しずつ見えてくるようになるのが、この上棟後です。
建て方では、あらかじめ加工が行われた柱や梁を現場で組んでいく作業になります。
建て方から上棟までは、2日程度で一気に組み上げていきますので、現場の確認もとても重要になってきます。
建て方工事中や上棟後にしっかりとチェックしましょう
・ 耐力面材の施工
地震の力などに耐えるためにそと壁に面材を施工する施工者も増えていますが、この面材がしっかりと力を発揮できるように、柱や梁にしっかりと固定されなければなりません。
固定の方法にも細かな規定がありますので、チェックポイントで確認してください。
<スポンサードリンク>
・ 筋かいの施工
耐力面材が増えてきたものの筋かいはまだ一般的に使用されています。
筋かいは、金物を使って留め付けなければいけませんので、筋かいが入っているかはもちろん、金物を使っているかをチェックするようにして下さい。
e.屋根工事
・ 野地板の施工
野地板施工とは、屋根からの雨漏れや台風で屋根が飛んでいくのを防ぐためにとても重要な工事です。
野地板がしっかりと留め付けられているか(150mm以下の間隔で釘やビス留め)
をチェックしましょう。
また、野地板の接合部は、防水テープなどの施工は雨漏れに対して有効です。
・ ルーフィングの施工
ルーフィングは、屋根を雨から守るためのシートです。
基本的には、屋根材は雨を完全に防いでくれるわけではなく、このルーフィングの表面までは雨が入ってくるものと考えてなければなりません。
ルーフィングの施工にも雨が侵入しないための重要なポイントがありますので、しっかりと確認が必要です。
<スポンサードリンク>
f.建具工事
・ 外窓・玄関・勝手口の施工
窓の取り付けは、雨の侵入を防ぐための大切な工事になります。
窓の取り付け前に、防水シートや防水テープが正しく施工されているかを確認しましょう。
また、将来に渡って窓などの開け閉めに不具合なく行うために、その窓を支える構造(窓台・窓まぐさ)にも注意が必要です。
・ 内装建具の施工
内装建具とは、室内ドアや窓とその枠のことで、歪みなく垂直に木下地につけられているかを確認する必要があります。
少しのゆがみであれば建具側で調整がききますが、その歪みが大きいと、ドアの上と下で隙間が違って不格好だったり、ロックを外すと自動的に開いてしまうようなドアになってしまう危険性があります。
また、将来に渡って開閉が困難にならないように、下地にしっかりと固定されているかを確認するようにしてください。
g.外壁工事
<スポンサードリンク>
・ 外壁防水シートの施工
一部の外壁材を使用する場合を除いて、一般的に透湿防水シートの施工が行われます。
このシートは屋根のルーフィングと同様、雨が侵入することを考慮して施工する必要があります。
シートの施工の方法が細かく決められていますので、確認してください。
・ 通気胴縁の施工
外壁の通気胴縁とは、壁の中の水蒸気を適切に排出して壁内結露を起こさないために外壁材と防水シートとの間に空気を通すための空間を確保するために施工します。
そのため、外壁の下部分から入った空気が上まで抜けるような施工がされているかを確認する必要があります。
・ 外壁貫通口の隙間処理
雨や空気が自由に出入りしないためにも、外壁に設けた貫通口の処理をしっかりとしなければなりません。
貫通口には、スリーブパイプなど、処理のしやすい部材を用いて、シーリングだけでなく、テープや専用部材を用いた施工が望ましいです。
・ 外壁材の施工
胴縁に外壁材を張り上げていきますが、外壁の種類によって留め付け方法が指定されています。
誤った施工をしてしまうと、見かけの問題だけでなく、 水が侵入し、胴縁が腐って外壁が脱落するなどの不具合に繋がるので、施工マニュアルを確認しながら現場をチェックする必要があります。
<スポンサードリンク>
h.塗装工事
・ 外壁塗装
外壁を塗装する場合は、塗装するペンキが板金部分やサッシに付着すると侵食される可能性がありますので、しっかりと養生が必要です。
また、外壁塗装の際には、必ず塗装のために養生シートを足場などに掛けるのですが、風向きや風の強さによっては、養生をしていない方法に飛散する場合もあります。
塗装をされる方が近隣に注意しているかどうかを確認しましょう。
i.内装工事
・ 造作家具
造作家具は、既製品を買って取り付けるものではなく、現場で大工さんなどが木材などを組んで造りつける家具のことです。
(「造りつけの家具」と呼ばれたりもします)
図面でしか確認できない部分のため、棚の位置や出幅などを使い勝手を考えながら現場で確認するようにしましょう。
また、しっかりと下地に固定されているか、コンセントなどの使い勝手なども確認しましょう。
・ クロス施工
<スポンサードリンク>
クロスを貼る前には、いくつかの工程があります。
1、パテ埋め
石膏ボードの突き合わせ部分やビス留め部の隙間を埋める。
すべての凹凸に対してパテ埋めされているかを確認しましょう。
2、クロス貼り
クロスに糊を付けてクロスを貼っていきますが、クロスの継ぎ目はどうしても出てきます。
その継ぎ目が目立たないところになっているかを割り付け図などで事前に確認しましょう。
3、仕上げ
クロスの糊が残っていると、数年経過するとその部分だけ汚れが目立つことになります。
貼った直後は分かりにくいのですが、しっかりと糊の残りを拭きあげているか確認しましょう。
j.断熱工事
・ 断熱材の施工
断熱材は種類によって施工方法が大きく異なります。
繊維系断熱材などには、標準施工マニュアルが 「ガラス繊維協会」や「ロックウール協会」などから出されていますので、事前に確認するといいでしょう。
また、断熱材の施工ミスで多いのが、断熱材の垂れさがりや留め付け位置の間違いです。
断熱材と建材の間に外の空気が入り込むような施工になっていると断熱の効果は著しく低下しますので、しっかりと確認しましょう。
<スポンサードリンク>
断熱材の種類や施工方法は以下のページで確認ください。
・ 気密シートの施工
気密シートとは、家の中の湿気た空気が壁の中に入って壁内結露がおこるのを防止するためのシートです。
繊維系断熱材を使う場合は、必須ですので、施工されているかどうかをチェックして下さい。
その施工がしっかりと行われているかは、気密測定によって確認することができます。
以下のページで気密について詳しく紹介しています。
k.電気工事
・ 配線工事
電気の配線は、天井や壁の石膏ボードをを貼る前に施工します。
将来リフォームする際に、どこにどれくらいの容量の配線が通っているのかが分かるように図面と実際の現場の相違がないかを確認しましょう。
・ 配管工事
ここでいう配管工事とは、24時間換気システムやダクトを使った換気扇のためのものです。
<スポンサードリンク>
換気は法律に適合しているかの確認が必要になっていますが、その時に配管の長さや曲がりの数などを決めて計算しています。
そのため、図面通りに施工していないと、新鮮な空気が入ってこない、炊事のニオイがいつまでたっても抜けない、湿気がこもるなど『法律に適合しない家』にいなる危険性もありますので、配管の長さは図面通りか、配管が潰れていないか、曲げの数は図面通りかを確認してください。
l.給排水工事
・ 配管スリーブの施工
配管は、基礎のスラブを貫通させて立ち上げるようになっています。
配管の位置が正しいのかを基礎伏図などで確認してください。
・ 配管工事
配管工事とは、主管から分岐したさや管を各部へ繋ぐ工事です。
水漏れの原因として、接合部がしっかりと留め付けられていなかったり、水が正しく流れるような勾配(水勾配)を確保していなかったりする場合がありますので、確認が必要です。
単なる接続忘れで、基礎の中がプールのように水が溜まってしまうことに繋がりますので、しっかりとチェックしましょう。
<スポンサードリンク>
m.ガス工事
・ スリーブ配管工事
給排水工事と同様に、基礎のスラブを貫通させてガス管を立ち上げる工事になります。
位置が適切か、配管の太さは図面の通りかなどを確認してください。
・ 配管工事
立上げ部分からガス使用機器の接続を行う作業です。
数がそれほど多くないことや、検査が行われることから異常が見つかることは少ないですが、図面通りに配管されているかを確認しましょう。
n.外構工事
・ ポーチ
玄関のポーチなどの下地を作る工事です。
通常は、タイルなどの仕上げ材があるので、凹凸の調整は仕上げの時に行います。
・ 門扉・車庫・造園工事
建物が完成した後に行う方も多いですが、道路との高低差があるなど敷地によっては、建物の工事の完成に合わせて工事を行う場合もあります。
カタログなどで確認していても、実際に現場で施工するとイメージが違う場合もありますので、現地で確認と打合せをしておく方がいいでしょう。
<スポンサードリンク>
現場のチェックのタイミング
仕事をしながら現場にも足を運ぶとなるととても大変だと思います。
現在お住まいの家と家を建てる土地が近ければ 頻繁に現場に行くこともできると思いますが、そういった方ばかりではないと思いますので、どの時期に現場にいけばいいのかをまとめてみました。
◆ 必ず現場にいくタイミング
・ 地鎮祭
土を掘り返すことに対して、地の神様を鎮めるための儀式でその家を建てるご家族が行うものですので、必ず現場に立ち会う必要があります。
なお、この際に、地縄などを行いますので、家の位置を確認するようにしてください。
・ 上棟式
上棟式とは、家の棟が上がったことを祝う行事で家を建てるご家族が家を施工する方を招く形で行われます。
上棟の際には、構造の重要な部分を組み上げていきますので、各部位を確認するようにしましょう。
・ 竣工式
<スポンサードリンク>
竣工式とは、引き渡しを受ける日です。
晴れて建てた家がご家族に引き渡される式で、 この段階で、所有者が施工者から家を建てたご家族へと移ります。
引き渡し前に不具合がないかをチェックし、竣工式までに出来る限り手直しがないようにしておくといいでしょう。
◆ 現場のチェックのタイミング
現場のチェックポイントは他のページで詳しく紹介しますが、ここでは、どのタイミングで現場のチェックをすればいいのかを紹介します。
細かなチェックができなくても、隠れてしまう部分を写真に撮っておくとなにかあったときに参考にすることができます。
出来る限り現場に行って、図面を片手に写真を撮るようにしてください。
☆ 地盤改良時
地盤の改良が必要な場合で杭などを打ち込む場合には、設計通りの長さで打ちこまれているか、場所は間違っていないかなどが確認できます。
☆ 基礎のコンクリート打ち時
ここでは、コンクリートを流すと見えなくなる鉄筋の確認などができます。
見えなくなる前に確認して写真を撮っておくことが重要です。
<スポンサードリンク>
☆ 上棟時
ここでは、隠れてしまう梁や柱などの構造材のせいが図面通りになっているか確認しましょう。
また、柱と梁の接合部や筋交いの取り付け部などにはかならず金物が入っています。
ボルトや釘、ビスで確実に止められているか確認しましょう。
☆ 屋根葺き工事時
雨漏れが起こらないように施工されているかは、屋根材を葺く前に確認すると分かります。
水の流れをイメージして、下地の材料が正しく施工されているか確認しましょう。
☆ 外壁の下地施工時
屋根同様、施工の不具合によって雨漏れが生じる危険性があります。
防水シートの施工や、窓周りの防水処理などを確認しましょう。
☆ 外壁の施工時
外壁は火災の時に延焼を防ぐ役目もあります。
<スポンサードリンク>
そのため、設計通りの厚みの外壁材が施工されているかを確認しましょう。
☆ 断熱材施工時
断熱材の施工の方法は細かく規定されています。
施工マニュアルなどを参考にしながら、現場の確認をしてください。
☆ 木下地工事完了時
天井や壁に石膏ボードなどの仕上げ材を貼る前に、下地がしっかりと組まれているかを確認しましょう。
また、絵を飾る部分や造作建具を付ける部分などがしっかりと補強されているかもチェックするようにしましょう。
この時期になると、給排水の配管作業も終わっていますので、ボンドなどを使いしっかりと接続されているかあわせて確認するといいでしょう。
☆ 竣工2~3週間前
気になるような傷がないか、扉の開閉はスムーズかなどを確認しましょう。
基本的には、「構造」「防火」「防水」「断熱」といった家の基本性能に関わる部分が確認できる時期を挙げています。
<スポンサードリンク>
現在作成中ですが、 ご自身でチェックできるようなチェックシートを近く公開したいと思います。
最終更新日 : 2011年5月9日