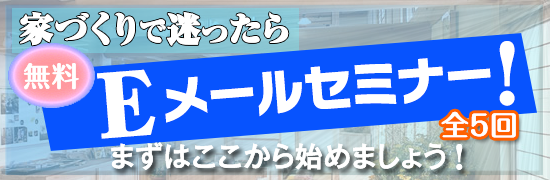現在、建築基準法ではシックハウス症候群を予防する意味で、
換気扇の設置が義務付けられています。
また、これとは別にビル衛生管理法では
居室の二酸化炭素の濃度は、1000ppm(0.1%)以下に抑えるように
空気を浄化することが、規定されています。
二酸化炭素の濃度が1000ppm(0.1%)を超えると、
眠気が襲ってくると言われており、空気環境としては悪くなります。
更に、3~4%を超えると、頭痛・めまい・吐き気など実際に体に
危険な状態となると言われています。
そこで、実際に一体どんな場合に、1000ppm(0.1%)を超えてくるのかを
実測してみました。そこから見えてきたのは、如何に換気が大切かと
いう事実でした。
寝室の二酸化炭素濃度
平成11年に建てられた、鉄骨2階建て(積水ハウス)の共同住宅のある一室(53.5㎡)。
平成24年9月、
寝室に二酸化炭素濃度測定器を設置。
<スポンサードリンク>
寝室の扉は開き、53.5㎡の居室の扉は全て開く。
寝室には大人2名が就寝。
就寝時間から起床に至るまでの二酸化炭素濃度を測定。
寝室内の換気扇は無し。窓は全て閉める。
トイレの換気扇のみ稼働。(トイレの扉は閉)
暖房などの機器は使用無し。
この時の、二酸化炭素を計測した結果は、以下の通り。
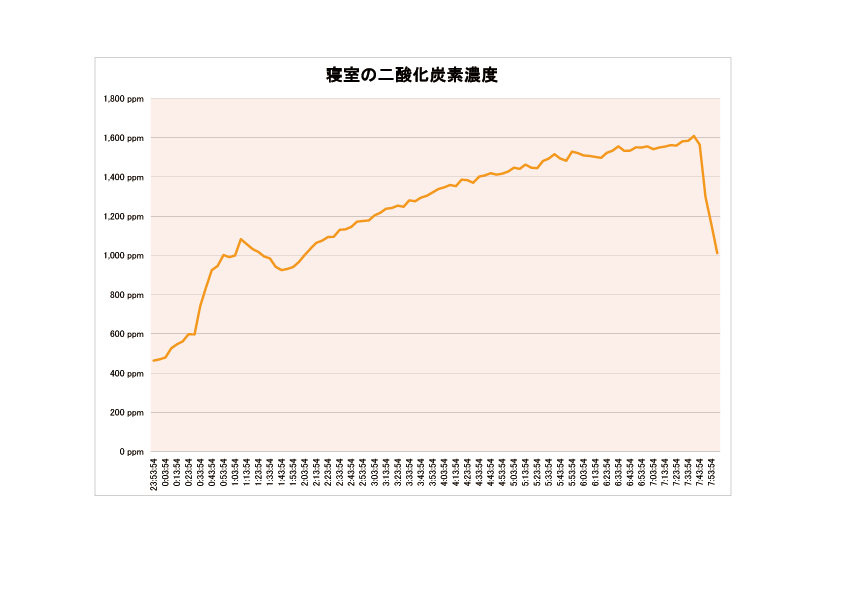
【結果の考察】
・大人二人が部屋にいると、扉を開けていても1000ppmは簡単に超えてしまい、
二酸化炭素濃度は過剰状態となる
・換気扇が居室に設置されていないと、空気の滞留が起こり、二酸化炭素濃度が濃くなる。
これは、平成11年の気密を意識していない住宅で生じていることであり、
この時期の建物は、意識していないにも関わらず、気密性能が高い事が分かる。
・空気が滞留しているため、扉を開けていてもあまり二酸化炭素濃度が有効的に薄くならない。
・この状態の住宅に、開放型の燃焼機器(ガスファンヒーターやストーブ、コンロなど)を
使用することは、かなり二酸化炭素濃度が濃くなる事が予想できる。
<スポンサードリンク>
二酸化炭素濃度を有効に減らす方法
上記の結果を踏まえ、今度は二酸化炭素の濃度を有効に減らす方法を調べてみた。
同様の建物のリビングに二酸化炭素濃度測定器を設置。リアルタイムで確認する。
大人一人が在室時には、800ppm程度。
大人二人になると、1000ppm~1500ppmへと上昇。
これを1000ppm以下に減らすために、まずはリビングの掃き出しサッシを
一窓開放する。
外部からは、冷気が入ってくるものの、二酸化炭素の濃度はほとんど変化なし。
10分程度過ぎても変化が無いので、リビングの他方角にある窓をもう1窓開ける。
この日は、風が特に吹いておらず室内を吹き抜ける感覚は無い。
10分程度過ぎても、ほとんど二酸化炭素濃度に変化は無かった。
続いて、キッチンに設置している換気扇を弱運転で起動する。
すると、5分もしないうちに二酸化炭素濃度がみるみる下がっていく。
大気の二酸化炭素濃度とほぼ同じ、500ppm程度で落ち着く。
【結果の考察】
・大人が二人いると、多少広い空間でも直ぐに1000ppmを超える
・風の吹いていない日は、温度差が多少あっても窓を開けた程度では有効な換気となりにくい
・最も有効な二酸化炭素濃度を減らす方法は、換気扇を起動させることである
<スポンサードリンク>
- 大人二人以上いると、二酸化炭素濃度が1000ppmを超えることが割りとよくあると考えられる
- 西洋型の現代住宅は、気密を意識していなくても十分に二酸化炭素が溜まりやすい住宅になっている
- 自然換気は季節によって殆ど期待できない
- 二酸化炭素の濃度を有効に減らす方法は、機械換気である。
- 平成14年以降の換気扇設置が義務付けられた住宅以前の建物は、開放型の燃焼機器(ガスファンヒーター、コンロ、ストーブなど)を使うことは危険と思われる。
上記を踏まえると、
『住宅は隙間だらけのスカスカの家を作る』
か、
『高気密とし、換気扇でしっかりと換気の出来る家にする』
ことが大切であることが分かる。
冬の寒さを考えると、しっかりと高気密化し換気扇を動かして暮らすことが一番と言える。