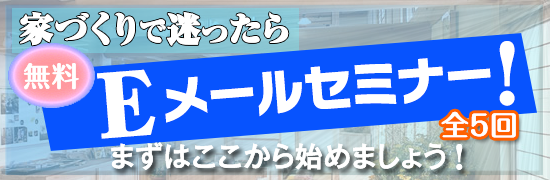Home > 固定資産税、都市計画税
|
tax
建物や土地を所有していると必ず納めないといけないのが『固定資産税』と『都市計画税』です。 固定資産税や都市計画税は土地や建物の評価額によっては課税額も大きくなりますので、年間の家庭の支出を計算する時には予め計画に入れておいた方がいいでしょう。 このページでは、固定資産税や都市計画税の税額や軽減の制度など詳しく紹介します。 |
|
|
目 次 |
|
<スポンサードリンク>
固定資産税
◆ 固定資産税とは
固定資産税とは、建物や土地を保有する方に課税される地方税です。
建物と土地でそれぞれ課税されますが、標準税率は同じです。
ただ、現在建物と土地でそれぞれ固定資産税の軽減を受けることができますので、
しっかりと確認してください。
また、固定資産税は、各年の1月1日現在に土地や建物を保有している方に対して
課税されます。
つまり、12月に建物や土地の引き渡しを受けるよりも1月2日以降に引き渡しを受けた方が
固定資産税は得だと言えます。
ただし、すでに土地を購入されている方は条件によって税金を多く支払うことになる場合もあります。
土地や建物の評価額などによって条件が変わりますので、
詳しくは以下の「◆ 固定資産税の軽減」でご確認ください。
◆ 固定資産税の税額
固定資産税の税額の算出方法は、以下の通りです。
評価額 × 税率 (※)
<スポンサードリンク>
※ 標準税率は1.4%となっていますが、この税率は地方自治体によって決められます。
なお、以前は税率の上限が2.1%までと定められていましたが、
平成16年の制度改正によって廃止されています。
<計算例>
「評価額が2,000万円の土地」と「1,500万円の建物」を所有している場合
標準税率の1.4%を使って計算すると
土地の固定資産税 28万円
建物の固定資産税 21万円
年間 49万円
課税されることになります。
ただ、この固定資産税にも軽減措置がありますので、下の『◆ 固定資産税の軽減』で確認してみましょう。
◆ 固定資産税の軽減
節税のためには、対象となる軽減を受けることが重要です。
原則として、申請を行わなければ軽減を受けることができませんので、
対象となる方は申請を行うようにしましょう。
◇ 固定資産税の軽減対象となる土地
☆ 土地
・ 住宅用地であること
・ 建替のために工事を行っている土地 ※
<スポンサードリンク>
1月1日の段階で、工事中の土地や建設予定地は原則として住宅用地の特例が適用されません。
しかし、一定の要件に該当する場合には、住宅建替え中の土地として、
住宅用地の特例が適用になりますので、「固定資産税の住宅用地等申告書」で申告を行ってください。
(一定要件の概要)
- 前年度の1月1日の段階で住宅用地であった
- 建替え前の住宅の敷地と同一の敷地で新築
- 前年度の1月1日段階で建替え前の住宅の所有者と同一の者(もしくは民法725条にいう親族等)が建替え後の翌年度の賦課期日における住宅の所有者である
- 当該年度の1月1日現在、住宅の新築工事に着手している(なお、確認申請書を提出しており、3月末日までに住宅の新築工事に着手するものについては、同様の取扱いをすることがあります)
- 住宅の新築工事が、次の年の1月1日までに完了すること。ただし、複数年にわたり新築工事がなされる場合については、住宅の新築工事が、確認申請書に記載された新築工事完了予定年月日の後に初めて到来する年の1月1日までに完了すること。
これらの要件については、各市町村の主税局にお尋ねください。
|
1月1日現在に、以下の条件に当てはまる土地を言います。 『居住するための建物が建つ土地で、その建物の床面積の10倍までの土地』 つまり、土地を購入し新築する場合で、1月1日現在に工事中の場合は、 住宅用地の場合は、固定資産税や都市計画税の軽減を受けることができますので、
また、店舗併用住宅などの場合は、 建物全体の床面積に対して、 |
<スポンサードリンク>
☆ 建物
以下の条件を満たす場合に軽減を受けることができます。
- 居住部分が床面積の1/2以上
(店舗などと併用する場合) - 床面積が50m2以上280m2以下
(貸家のマンション、アパートなどの共同住宅の場合は40m2以上280m2以下) - 平成24年3月31日までに新築された建物
◇ 固定資産税の軽減措置
☆ 土地
以下割合で課税標準額が減額されます。
| 名称 | 面積区分 | 課税標準額の軽減割合 |
| 小規模住宅用地 | 200m2までの住宅用の土地 | 1/6 |
| 一般住宅用地 | 200m2を超え住宅の床面積の10倍まで | 1/3 |
<計算例>
固定資産税の税額の計算例と同様に例を上げて確認しましょう。
評価額が2,000万円、広さが120m2だった場合、
2,000万円 × 1/6 × 標準税率1.4%
<スポンサードリンク>
ですので、土地の固定資産税は、
46,666円(円未満切り捨て)
となります。
軽減の申請をしないと土地の固定資産税は28万円なので、
軽減の申請することで23万円強が節税できることになります。
☆ 建物
以下の割合で、固定資産税が軽減されます。
| 建物概要 | 床面積の制限 | 固定資産税の 軽減額 |
適用期間 |
| 認定長期優良 新築住宅 |
120m2相当分まで | 1/2 | 5年度分 |
| 認定長期優良 新築住宅 3階以上の耐火・準耐火建築物 |
120m2相当分まで | 1/2 | 7年度分 |
| 新築住宅 | 120m2相当分まで | 1/2 | 3年度分 |
| 新築住宅 3階以上の耐火・準耐火建築物 |
120m2相当分まで | 1/2 | 5年度分 |
<計算例>
固定資産税の税額の計算例と同様に例を上げて確認しましょう。
評価額が1,500万円、床面積が120m2だった場合、
1,500万円 × 標準税率1.4% × 1/2
ですので、建物の固定資産税は、
105,000円
<スポンサードリンク>
となります。
軽減の申請をしないと土地の固定資産税は21万円なので、
軽減の申請することで10万5千円が節税できることになります。
都市計画税
◆ 都市計画税とは
都市計画税とは、道路や下水道、公園などの都市計画にかかわる工事に対して使われる税金で
市街化地域にある土地や建物に対して課税されます。
また、都市計画税の納税対象は、各年の1月1日現在に土地や建物を保有している方となっています。
これは、固定資産税と同じです。
1月2日に売却したとしても1年分の固定資産税や都市計画税は
「1月1日に所有していた方」に課税されますので、ご注意ください。
◆ 都市計画税の税額
都市計画税の税額は、お住まいの市町村によって異なります。
なお、この都市計画税は課税していないところから0.3%までを上限に決められています。
市町村の管轄税務署のホームページなどで確認できますので、
確認してください。
<スポンサードリンク>
なお、税額の計算方法は土地、建物も同様で、
価格 × 税率
で求められます。
また、都市計画税は、土地のみ軽減措置がありますので、
『◆ 都市計画税の軽減』でご確認ください。
◆ 都市計画税の軽減
都市計画税では、土地のみ軽減措置があります。
以下割合で課税標準額が減額されます。
| 名称 | 面積区分 | 課税標準額の軽減割合 |
| 小規模住宅用地 | 200m2までの住宅用の土地 | 1/3 |
| 一般住宅用地 | 200m2を超える住宅用地 | 2/3 |
土地や建物の評価額について
◆ 評価額(価格)はどのように決まるか
◇ 評価額の決定方法
固定資産の価格は、
総務大臣が定めた『固定資産評価基準』に基づいて評価された額を、
知事又は市町村長が決めます。
<スポンサードリンク>
その後、固定資産課税台帳に決定額が登録され、
課税される元となる評価額となるのです。
この評価額は、3年に1度見直しがなされますが、
次回は平成24年に行われる予定です。
原則としては、3年間その評価額が据え置かれることとなっていますが、
急激な地価の上昇や下降などが生じた場合やリフォームなどを行った場合は、
評価額をその都度変更するようになっています。
もう少し具体的に知りたい方のために、
建物と土地の評価額の決定方法を紹介します。
◇ 土地評価額の計算方法
土地の評価額を計算には、「市街地宅地評価法の路線価方式」と呼ばれる評価方法を採用するのが
一般的です。
簡単にいうと、国税局が定める道路の価格を目安に、その土地の用途地区の区分や、
形状、法的制限などを考慮した画地補正率を加味して単位面積あたりの評価額を算出する方法です。
以下の方法で大よその評価額を計算してみてください。
1.評価額の算出のために使われる路線価を調べる
路線価は、全国の税務署で公表されています。
そのため、税務署まで足を運ぶと無料で閲覧できます。
また、国税庁のホームページでも路線価が確認できます。
すべての道路を網羅しているわけではないので、もしここで見つからない場合には
税務署まで足を運ぶ必要があります。
また、相続などを専門に扱う会計事務所などでも路線価表を置いているところがあります。
<スポンサードリンク>
2.画地補正率表から補正率を確認する
◇ 建物評価額の計算方法
評価額の計算には、
計算する年にその建物を再度建築した場合にかかる建築費を基準に
築年数を考慮した係数を掛けて計算されます。
<計算式>
| 建物の評価額(価格) = (基準年度の前年度における単位当たり再建築費評点) × (再建築費評点補正率) × (経年減点補正率) × (床面積) × (評点一点当たりの価額) |
※ 東京都主税局ホームページを参考
◆ 評価額の目安
◇ 土地の評価額の目安
土地の固定資産税評価額は、国の示すその土地の適正な価格(路線価)の
70%を基準に決定されています。
◇ 建物の評価額の目安
<スポンサードリンク>
☆ 新築時
新築後の評価額は、建築費の50~70%を目安にするといいでしょう。
なお、評価額を決定するための家屋調査ですが、
その建物に使われた資材やその量、設置される住宅設備機器などが
チェックされます。
引き渡しを受けた後、図面を持った専門調査員の現地調査を受ける必要が
ありますので、ご注意ください。
原則として一度家屋調査を終えた建物は、3年ごとの評価額の見直しの際
建築物価の変動及び経過年数に応ずる減点補正率によって見直しが行われるため、
家屋の状況が変わらない限り再度家屋調査を行うことはないとされています。
☆ 建物の評価額の変化
| 建物の評価額(価格) = (基準年度の前年度における単位当たり再建築費評点) × (再建築費評点補正率) × (経年減点補正率) × (床面積) × (評点一点当たりの価額) |
※ 東京都主税局ホームページを参考
にて計算されるようです。
年数が経過すると評価額が下がることが一般的ですが、
それは、経年減点補正率が徐々に低く変更されるためです。
なお、この経年減点補正率は、
木造住宅の場合新築されてから25年、コンクリート造の共同住宅は60年で下限の20%まで下がります。
つまり、木造住宅の方がコンクリート造のマンションなどに比べて、
評価額の落ちるスピードは早いということが言えるのです。
<スポンサードリンク>
最終更新日 : 2011年11月4日