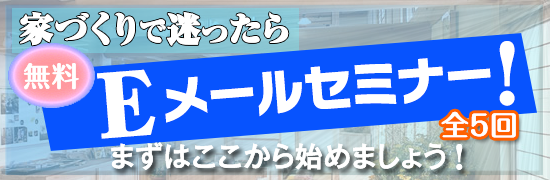Home > 住宅の設備機器の比較と選び方 > オール電化vsガス併用(ウィズガス)
|
all denka VS with gas
新築を建てる時迷うのが、「オール電化」にするか「ガス併用」かだと思います。 一概にどちらが良いとは言えず、各家庭の生活スタイルや好みによって変わってきます。 では、あなたはどちらを選ぶ方がいいのかを知って頂くために、 さて、あなたはどちらを選びますか? |
|
|
目 次 |
|
オール電化の生活
<スポンサードリンク>
◆ オール電化とは?
オール電化とは、家にガスは引かず、家庭のすべてのエネルギーを電気でまかなう生活です。
オール電化住宅で設置する設備機器は、以下のようになります。
| 給湯 | エコキュート、電気温水器 |
| 調理 | IHクッキングヒーター、ラジエントヒーター |
| 冷暖房 | エアコン、蓄熱暖房機、 ヒートポンプ式温水暖房(床暖、パネルヒーター)など |
オール電化の2010年の普及率は、戸建の新築が最も高く、8割を超える地域もあるようです。
集合住宅などを含めた新築の普及率は50%程度となっていますが、
電力不足の影響もあって、2011年の増加率は下がるとみられています。
では、オール電化住宅での暮らしはどうなのでしょう。
それぞれの設備機器の特長を見てみましょう。
◇ IHクッキングヒーターの特長

☆ IHクッキングヒーターとは?
そんな多くの方が選んでいるオール電化ですが、
やはり決め手はIHクッキングヒーターの便利さや掃除のしやすさを挙げる方が多いです。
IHクッキングヒーターはすでに多くの方がご存じの調理機になっていますが、どんな機器なのかおさらいをしてみましょう。
<スポンサードリンク>
IHクッキングヒーターは、電磁誘導加熱(Induction Heating)を使った調理器具のことです。
これだけ書いても良くわからないと思いますが、簡単に説明すると、電磁線を発生させるコイルが調理機の中に組み込まれていて、金属製の鍋などを近づけることで電気が流れます。
金属は電気抵抗がありますので、その抵抗によって熱が発生し(ジュール熱といいます)
鍋自体が温かくなるという仕組みです。
そのため、電気を通しやすい金属のようなものを置かない限り熱は出ませんので、
触っても熱くないのです。
また、電気抵抗によって熱が発生するため、抵抗の大きい鉄製の鍋やフライパンが推奨されているのは
そのためです。
☆ オールメタルとは?
現在は、「オールメタル」などといった鉄製以外の鍋で使えるIHクッキングヒーターも誕生しています。
このオールメタルでは、電気抵抗の小さいアルミや銅でも使えるのですが、
抵抗が小さくても加熱できるようにするために流す電流を強くしなければなりません。
そのため、効率が下がってしまい、調理にかかる電気代が上がってしまいます。
イニシャルコストやランニングコストを考えると、『鉄製の鍋に買い替える方がトータルでみるとお得』
と考える専門家もいます。
持っている調理用具を確認しながら検討しましょう。
☆ IHクッキングヒーターのデメリット
<スポンサードリンク>
IHクッキングヒーターのデメリットとしては、
・電磁波の影響が懸念される
・ガスコンロと比べると少し高めの価格
・ガスコンロよりも調理のニオイが拡がりやすい
・使うには慣れが必要
といったことが挙げられます。
◇ エコキュートの特長
☆ エコキュートとは?
「エコキュート」は、夜間の電気単価の安い時間に、
空気の熱を利用するヒートポンプを使ってお湯を作る給湯器です。
『深夜電力』+『ヒートポンプ』ですので、ランニングコストの安さが最大のメリットでしょう。
エコキュートが毎日勝手にお湯を作ってくれますので、日常の生活で特に煩わしい操作はいりません。
このエコキュートは、前述の通り、深夜にその日使うお湯を作るため、
そのお湯を溜めておくタンクが必要になります。
(ヒートポンプユニットとタンクが一体となった商品もあります)
☆ エコキュートの一般的なサイズ
一般的な容量は、
370リットル 3~5人用
<スポンサードリンク>
460リットル 4~7人用
が多く選ばれているようです。
また、エコキュートの大きさですが、
370リットルのヒートポンプユニットとタンクで
横幅160cm 奥行き80cm 高さ190cm
ほどのスペースを見ておかなければいけません。
敷地の条件によっては、奥行きがスリムな商品や横幅と奥行きが一回り小さくなったタイプなどを
選ぶこともできます。
☆ エコキュートのサイズの選び方
エコキュートは作ったお湯を使いきる方が効率よくお湯を作ることができます。
そのため、エコキュートのタンク容量は大は小を兼ねるといった選び方では
ランニングコストに差がでる可能性があります。
家族構成はもちろんですが、
□ お風呂を毎日入れて入る?シャワー生活?
□ 朝、髪を洗う?
□ お湯で食器を洗う?食洗器?
□ 近い将来に子供が家を離れる可能性は?
なども考慮するといいでしょう。
☆ エコキュートのデメリット
エコキュートのデメリットとしては、
・ガス給湯器と比べ、イニシャルコストが高い
<スポンサードリンク>
一般的なガス給湯器と比較し、イニシャルコストでおおよそ1.5~2倍です。
・お湯をそのまま飲用できない
貯湯式のもの全般に言えることですが、注意書きとして必ず記載されています。
タンク内の掃除を定期的に行ったとしても沈殿物は溜まりますので、
衛生面を重視されるのであれば、ガス給湯を検討される方がいいのではないでしょうか。
・ガス給湯器に比べ屋外の設置スペースが大きい
・お湯を使いきると電気単価の高い時間帯に追いだきをする必要がある
・隣地が近い場合、室外機の向きを検討する必要がある
・タンクを設置する場所には重さに耐えられるような土台が必要
・深夜に稼働するので騒音や振動の近所への配慮が必要
などがあります。
ガス併用(ウィズガス)の生活
◆ ガス併用(ウィズガス)の生活は?
オール電化の普及に伴い、ガス併用を選択される方が減っていますが、
使いなれたガス機器を新居でも使いたいという方は今でも多いです。
現在はオール電化が優勢ですが、ガス製造メーカーやガス機器メーカーも
新規商品を開発し対抗しています。
<スポンサードリンク>
では、新しい商品も含めガス併用の生活を改めて確認してみましょう。
太陽光発電システムが普及し始め、一般家庭で発電して利用する、売電するという暮らしを送る方が
増えています。
この家庭で電気を作る方法は実は太陽光発電だけではないのです。
最初に、ガスで発電する「エコウィル」と「エネファーム」についてご紹介します。
◇ エコウィルとは?
☆ エコウィルの仕組み
「エコウィル」とは車のエンジンと同じようにピストンを動かしてシャフトをまわし、そのシャフトが繋げられた発電機で電気を作ります。車はガソリンや軽油などの燃料を使いますが、エコウィルではガスを燃料にしています。
当然、エンジンを動かす訳ですから、排熱が出てきます。
エコウィルでは、その排熱を利用して、お湯を作っています。
そのため、エコウィルは、電気とお湯が同時に作れるのです。
☆ エコウィルの発電量
エコウィルは、最大1kWの電力を作ることができます。
エコウィルを取り付けた、家族が4人の家庭では、使用電力の3割~4割を賄うことができる量に相当するようです。(床暖房を使用した場合)
このエコウィルは、お湯を使う時間にあわせて電気を作るため、お湯や床暖房をほとんど使わない夏場、日中は発電量が下がってしまいます。
<スポンサードリンク>
ちなみに、1kWというと冷蔵庫や照明でほとんど使いきってしまう電力量なので、特に心配する必要はありませんが、エコウィルで発電した電気は、売電することができません。
☆ エコウィルのデメリット
エコウィルのデメリットはどんなところなのでしょうか。
・停電時には使えない
・ガス給湯器に比べてイニシャルコストが高い
・夏場や日中のお湯を使わない時間帯は電気をほとんど発電しない場合がある
・お湯をそのまま飲料用として使えない
・ガス給湯と比べ屋外に広い設置スペースが必要
・定期点検が必要
が挙げられます。
◇ エネファームとは
☆ エネファームの仕組み
エネファームはエコウィル同様、ガスで電気とお湯を作ることができるのですが、大きな違いは、発電の方法です。
エコウィルではガスエンジンを動かして発電していましたが、エネファームはガスから水素を取り出し、空気中の酸素と反応させることで電気を作っています。
作られた電気は太陽光発電同様、直流のため、一般家庭で使えるようインバーターで交流に変えて家庭のコンセントなどに供給されます。
<スポンサードリンク>
ガスから水素を取り出す時や酸素と反応させたときに熱が出ますので、その熱をお湯を作るために使っています。
また、タンクに溜めたお湯を使いきった場合のために、補助熱源機が付けられています。
そのため、お湯が無くなって出なくなるといったことはありません。
☆ エネファームの発電量
発電量はエコウィルと同様最大1kWです。
1kW発電するときに発生する給湯のエネルギーはエコウィルよりも小さく、
1.3kW程度となっています。
そのため、エネファームの場合には、一般家庭(4人家族)の6割ほどの電気を作ることができるようです。
オール電化、ガス併用(ウィズガス)のメリット・デメリット
オール電化、ガス併用(ウィズガス)のメリットとデメリットをまとめました。
| オール電化 | ガス併用 (ウィズガス) |
|
| メリット |
基本料金を電気だけにまとめることができる 火を使わないので、移り火などの心配が減る 火災保険の優遇を受けることが可能 |
慣れているため、誤使用の事故が少ない 停電時でも調理が可能 設置コストが低く抑えられる |
| デメリット |
停電の際には調理ができない 電気工事にコストがかかる 設置コストが高い |
調理中の移り火での事故の可能性 基本料金が電気とガス両方必要 設置コストが高い |
<スポンサードリンク>
なお、メンテナンスや期待耐用年数を気にされる方も多いのですが、
ガス器具と電気機器ではあまり差はありません。
どちらも1年の保証で期待耐用年数は8~10年ほどです。
最終更新日 : 2011年9月30日