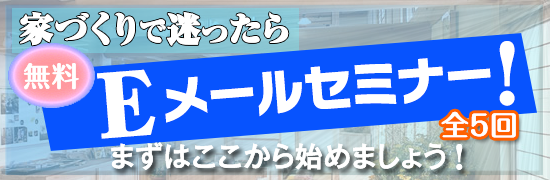Home > 家の仕様を選ぶための基礎知識 > 屋根の種類と比較
家を新築する、リフォームする際に検討したい屋根材の種類を知って、
比較してみましょう。
屋根材は種類によって初期費用もそうですが、
メンテナンスでも大きく金額が変わる部分ですので、
しっかりと比較して下さい。
屋根の種類と特長
屋根材は、建物を雨や火災から守る役目を持っています。
その役目を果たすために、屋根の勾配(傾き)が屋根材の種類ごとに
決まっています。
また、地震が起きたときには、
「その重さが倒壊などに繋がらない」ように
木造住宅の壁量を計算するときには屋根材の重さを加味して
計算するように定められています。
<スポンサードリンク>
主には、
- 外観をどのようにしたいのか
- 予算
- メンテナンス性
などから屋根材を選択する方が多いようです。
ここでは、代表的な屋根材の特徴を紹介します。
◆ 屋根の種類
☆ 粘土瓦
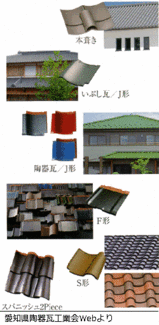
粘土瓦と言えば、
三州瓦(愛知県西三河)、石州瓦(島根県石見)、淡路瓦(兵庫県淡路島)の
日本三大瓦が有名です。
粘土瓦は、JISによって製造区分されていますが、
釉薬をかけて焼き上げた「釉薬瓦(陶器瓦)」
いぶすことで表面に炭化層をつくり独特の色合いを出すことができる「いぶし瓦」
陶器の自然な風合いを残した素焼き瓦などの「無釉瓦」
があります。
〇 陶器瓦(釉薬瓦)
【作り方】
<スポンサードリンク>
瓦の形に押し固めた粘土の上に釉薬をかけて、窯の中で高温で焼き上げたら完成
【特徴】
瓦表面に塗る釉薬がガラス質のコーティング材となりますので、
雨が瓦内部に浸透して割れたり劣化することがなく、
耐久性、対汚性に優れます。
【形・意匠】
J形(和形)、F形(平板)、S形等があり、
和風・洋風の外観に合わせた陶器瓦を選択することが可能です。
〇 いぶし瓦
【作り方】
瓦の形にかたどった粘土を窯で焼き、
その後、松材や松葉で燻して(燻化工程)表面に炭素膜を作って完成
【特長】
深い銀色で古くからお寺や日本家屋に使用されてきました。
安土桃山時代に織田信長が安土城を造らせた際に中国から伝わったという説が最も有力らしいのですが、
その歴史は1400年以上と非常に古いものになります。
現在は、松材などで燻すのではなく、
LPガスなどの炭化水素を含む工業製品を代用したものが多く製造されているようです。
いぶし瓦は、表面を覆う炭素膜によって、防水や色彩を保っていますが、
炭素膜の劣化が瓦の寿命となります。
陶器瓦の耐久性が半永久的であるのに対し、
いぶし瓦は、30 ~50年ほどではないでしょうか。
<スポンサードリンク>
【形・意匠】
本葺形、J形(和形)、S 形、F形(洋形・平形)などがありますが、
いぶし瓦で多いのは、本葺形、J形(和形)でしょう。
本葺形とは、神社や仏閣などで見ることができますが、
平瓦(女瓦)と丸瓦(男瓦)を使った瓦葺きが一般的で、
屋根の重さもかなりのものになると思いますが、
その分重厚感漂う外観を作り上げることができます。
〇 無釉瓦(素焼き瓦)
【作り方】
瓦の形をかたどった粘土を酸化炎焼成して完成
※酸化炎焼成は、陶器を焼くときに酸素を十分に供給した状態で焼成する
方法です。
【特長】
粘土をそのまま窯で焼くため、光沢のない優しい朱色の自然な仕上がりが特長的です。
スペインやフランスなどのヨーロッパの瓦ではよく見られるものです。
耐久性は比較的長く、40~50年とされています。
【形・意匠】
日本でもS形が製造されています。
素焼き瓦によって、ヨーロッパ調の外観の雰囲気に仕上げることができるため、
ヨーロピアンの住宅にしたい方にお勧めです。
<スポンサードリンク>
☆ スレート系
スレートとは、粘板岩の英語で、粘板岩を屋根に載せたものをスレート葺と言います。
スレート葺と聞くと、クボタ松下のカラーベストなどをイメージされる方も多いと思いますが、
これは、化粧スレートと言い、人工的に造られた屋根材で、
天然スレートと化粧スレートは葺き方や見た目が少し似ているだけの
全くの別物とお考えください。
〇 化粧スレート(カラーベスト)
【作り方】
セメントに繊維材料を混ぜ込み、高温で成形して冷まして完成
【特長】
9mm以上といった規定はあるものの、陶器瓦などと比べると非常に軽く、
価格も安いといったことが挙げられます。
化粧スレートのことをカラーベストという方が多いのですが、
カラーベストとは、旧クボタの商品名で、圧倒的な販売量のせいで
「化粧スレート=カラーベスト」と認識している方が多いためでしょう。
知名度に差はありますが、シャーペンやウォークマンと同じですね。
<スポンサードリンク>
耐久性ですが、30~50年と技術進歩とともに伸びてきました。
ただ、美観を保つための塗装は必要で、
塗料の種類によりますが、8~20年に1度の塗り替えが必要な商品が一般的ですが、
トップコートを紫外線による劣化を抑えたものなどがあり、
30年間塗装なしでも使えるといった商品も存在します。
塗料と塗りかえ時期は、「外壁材の塗りかえ」を参考にして下さい。
【形・意匠】
形状は、平型が一般的です。
凹凸が少ない化粧スレートですっきりとした外観を作ったり、
凹凸の大きな化粧スレートで、重厚感を持たせたり
和風、洋風どちらでも対応可能です。
〇 天然スレート
【作り方】
粘板岩(玄昌石)を薄く板状に加工して、出来上がり
【特長】
天然石ですので1枚1枚表情が異なり、それに魅力を感じる方も多いでしょう。
また、酸やアルカリにも強く、水を通しにくい材料のため、耐久性も非常に高い
材料です。
日本ではそれ程天然スレート葺は普及していませんが、
ヨーロッパではそこそこ見ることができるようです。

日本では、東京駅が有名。
高価で、重い材料のため、それを考慮した構造が必要になるでしょう。
【形・意匠】
住宅で天然スレートを活かす方法は、正直経験がないため分かりません。
天然スレートを採用したい方は、
採掘している方にアドバイスを受けることをお勧めします。
☆ 金属系
金属系の屋根材には、鋼板と非鉄金属があります。
現在、鋼板では、ガルバニウム鋼板が一般的ですし、
非鉄金属では、銅板を見かけることがあるのではないでしょうか。
〇 ガルバリウム鋼板
【作り方】
心材の鉄にめっき層を施して完成
【特長】
心材となる鉄の腐食を防ぐために、
アルミニウムと亜鉛、珪素で防食性を持たせた鋼板です。
1972年にアメリカで開発され日本に入ってきましたが、
近年のステンレスや銅の価格高騰などにより、
ガルバリウム鋼板への切り替えが増えています。
開発メーカーから出されるめっき皮膜寿命ですが、
沿岸地域などの塩害が考えられる地域では15年、
工業都市、田園地域で25年となっています。
<スポンサードリンク>
【形・意匠】
葺き方もいくつかあります。
一文字葺き、亀甲葺き・菱葺き、立平葺き、瓦棒葺き、波板葺き、折板(せっぱん)葺き
段葺き、横葺き、金属瓦葺き、溶接葺き
などがあります。
〇 銅板
【厚み】
住宅で主に使用される厚みは、0.3~0.5mm程度でしょう。
当然厚くなるほど、耐久性が上がりますが、価格も上がります。
価格と耐久性のバランスからいくと、0.35~0.4mmが優れるようです。
【特長】
古くから屋根や破風などに用いられることが多かった銅ですが、
銅の急激な値上がりから最近では使われることが少なくなってきました。
銅の表面に緑青が出てくると、住宅を落ち着いた雰囲気に見せることができるとともに、
経時劣化が非常に緩やかになり、耐久性が上がるという機能面でも期待できる材料です。
近年の酸性雨の影響などから銅板であっても穴が開くといった被害があるようですが、
酸性雨だけでなく、いぶし瓦と銅板を組み合わせることで、
銅の劣化を促進し、穴が開くなどの被害が考えられるようです。
屋根瓦との組み合わせも十分に注意するようにして下さい。
<スポンサードリンク>
耐久性としては、50年程度のようです。
0.4mm程度の厚みや下地をしっかりと施工すれば、100年持たせることも可能ですが、
釘を打つ位置や折り方など技術を持った専門の板金業者に依頼する方がいいでしょう。
【形・意匠】
ガルバニウム鋼板同様、様々な葺き方があります。
ルーフィングなどが施工できる場合は良いですが、もしできない場合には、
結露等で生じる水をどのように逃がすのか、葺き方、折り方を工夫しないといけないようです。
基本的には、和風のイメージに仕上がりますが、
洋風であっても、下屋の勾配がとれない部分などで採用されることもあります。
☆ セメント瓦
セメントは、砂とセメントを原料に作られた屋根材です。
厚形スレート、コンクリート瓦などがあります。
セメントは耐水性が低いため、塗装などで、水への対策が必要です。
〇 厚形スレート
【作り方】
セメント、砂などの原料を混ぜ合わせ、それを型枠に流し込んで、
圧力をかけて脱水、養生し、固まったものに塗装をして完成
<スポンサードリンク>
【特長】
熱を加えないため、膨張収縮の影響を受けにくく、
精度が高いといったことが最大の特徴ではないでしょうか。
価格や、バリエーションの豊富さは化粧スレートのほうが勝りますし、
見た目の重厚感は陶器瓦のほうが優れています。
また、定期的なメンテナンスが必要になるところなど、
あまりメリットとして挙げられることが少ないのが現状だと思います。
陶器瓦や無釉瓦よりも安くなっていますが、
メンテナンスにかかる費用を考えると、あまり総額に差は生じないでしょう。
【形・意匠】
J形(和形)、S形、F形(平板)などがあります。
洋風、和風など、どんな外観にも採用できます。
〇 コンクリート瓦
【作り方】
セメント、砂などの原料を混ぜ合わせたものをパレットに練り出し、
養生、塗装を行って完成
※塗料を原料に混ぜ合わせる方法もあります。
原料は、厚形スレートと同じですが、原料の配合割合が違います。
【特長】
厚形スレートと同じです。
<スポンサードリンク>
際立ったメリットは無いように感じます。
メンテナンスが必要になりますが、塗料をあらかじめ材料に練りこむ方法により、
メンテナンスのサイクルを伸ばすことができるようです。
ただし、20年程度
【形・意匠】
種類が少なく、F形(平形)のみのようです。
イギリスやオーストラリアなどの技術を日本で採用しているようですが、
あまりバリエーションは多くありません。
「街で見かけて気に入った家の屋根がコンクリート瓦だった」
などでないと、選択されないのかもしれませんが・・・
☆ その他
その他として、KMEWから販売されるROOGAなど、
工業製品が販売されています。
新製品は、陶器瓦などと比較すると、まだ価格が高めではありますが、
重量が軽いものやメンテナンスフリーなどのメリットを備えた商品が多いように感じます。
数年経過すると、価格も陶器瓦と変わらないくらいまで落ちてくると思いますが、
今でもコストパフォーマンスは高い商品だと思います。
<スポンサードリンク>
屋根の目安の金額
屋根の目安となる金額は以下の通りです。
比較のために、屋根材施工の材料と直接工事費のみの金額を紹介しています。
下地、樋、換気役物などにかかる費用は除いています。
◆ 瓦葺きの目安の金額
| 種類 | 目安(切妻) | 目安(寄棟) | 相場 |
| 陶器瓦 | 約 6,500 円 | 約 7,700 円 | 5,800 ~ 12,000円 |
| いぶし瓦 | 約 7,000 円 | 約 8,500 円 | 6,800 ~ 12,000円 |
| 無釉瓦 | - | - | 7,500 ~ 11,000円 |
※上記金額は、1m2あたりの単価の目安です
◆ スレートの目安の金額
| 種類 | 目安(切妻) | 目安(寄棟) | 相場 |
| 化粧スレート | 約 3,500 円 | 約 4,000 円 | 3,500 ~ 9,000円 |
※上記金額は、1m2あたりの単価の目安です
天然スレートは、石材の価格の差が大きいため、
販売・施工業者に直接確認してください。
<スポンサードリンク>
◆ 金属葺きの目安の金額
| 種類 | 葺き方 | 目安 | 相場 |
| ガルバリウム鋼板 | 瓦棒葺き | 約 3,500 円 | 3,500 ~ 5,000円 |
| 平葺き | 約 4,500 円 | 4,500 ~ 12,000円 | |
| 長尺横葺き | 約 4,500 円 | 4,500 ~ 13,000円 | |
| 銅板 | 平葺 | 約 20,000 円 | |
| 横葺 | 約 15,000 円 | 14,000 ~ 20,000円 |
※上記金額は、1m2あたりの単価の目安です
銅の価格変動が大きくなっています。
現在は、円高と不景気から、価格は下がってきているといえます。
◆ セメント瓦葺きの目安の金額
| 種類 | 目安 | 相場 |
| プレスセメント瓦 | 約 6,000 円 | 5,500 ~ 9,000円 |
| コンクリート瓦 | 約 7,000 円 | 6,000 ~ 8,000円 |
※上記金額は、1m2あたりの単価の目安です
屋根の比較
<スポンサードリンク>
特長を読んだだけではわかりにくいという方のために、
屋根材を簡単に比較できる表を作りました。
参考にしてみてください。
| 種類 | 重さ | 最小勾配 | 耐久性 | 耐風性 | 耐震性 | 価格面 | メンテ ナンス |
| kg/m2 | 分数勾配 | ||||||
| 陶器瓦 | 約40 | 4/10 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |
| いぶし瓦 | 約48 | 4/10 | ◎ | △ | 〇 | △ | 〇 |
| 無釉瓦 | 約49 | 4/10 | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 |
| 化粧スレート | 約25 | 3/10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 天然スレート | ◎ | 〇 | × | × | ◎ | ||
| ガルバリウム 鋼板 |
約5 | 2.5/10(平葺) 1.5/10(瓦棒葺) |
△ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 銅板 | 約5 | 〇 | ◎ | ◎ | △ | 〇 | |
| 厚形スレート | 約40 | 3/10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| コンクリート瓦 | 約45 | 3/10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
瓦の基本性能の中から特に気になるものをピックアップして
比較してみました。
長期的な目で見ると、陶器瓦がコストバランスに優れていると思いますが、
初期コストを抑えたい方は、化粧スレートを選択されるようです。
その他の性能についても紹介します。
【 断熱性能 】
<スポンサードリンク>
断熱性は、瓦自体の性能よりも、断熱材の施工や、通気層の確保がされているのかなど
設計のほうが重要になってきます。
【 遮音性 】
比重が重い材料ほど、遮音性能に優れます。
雨が屋根をたたく音などは軽量音ですので、屋根材の裏に断熱材を施工するなどすると
遮音には効果的です。
【 加工性 】
現場での加工性を考えると、金属系などの薄い材料のほうが優れています。
ただし、現場での加工性は、手間で費用換算できますので、
特に気にしなくていいのかもしれません。
屋根のメンテナンス費用の目安
屋根のメンテナンスですが、塗装するか、もしくは葺き替えかのどちらかになります。
どんな屋根でも塗り替えが必要かというとそうではなく、
陶器瓦はメンテナンスフリーで、下地の劣化が起こらない限り
半永久的に持つといわれています。
では、屋根の種類ごとにメンテナンスの必要な時期とおおよその費用をまとめましたので、
リフォームの際、新築の際の参考にしてください。
<スポンサードリンク>
| 種類 | メンテナンス時期 | 費用 |
| 陶器瓦 | 特に必要なし | - |
| いぶし瓦 | 炭化膜の寿命(40~50年)ごとに 葺き替え |
「屋根の目安の金額」を参照 |
| 無釉瓦 | 40~50年ごとに葺き替え | 「屋根の目安の金額」を参照 |
| 化粧スレート | 退色のための塗装 約15年 ※塗料により異なる |
約100万円 ※面積、屋根勾配、塗料の種類など によって異なる |
| ガルバリウム 鋼板 |
退色のための塗装 約15年 めっき寿命のための葺き替え |
塗装:約100万円 「屋根の目安の金額」を参照 |
| 銅板 | 葺き替え 50年 | 「屋根の目安の金額」を参照 |
| 厚形スレート |
退色のための塗装 約15年 葺き替え 約35年 |
塗装:約100万円 「屋根の目安の金額」を参照 |
| コンクリート瓦 |
退色のための塗装 約15年 葺き替え 約35年 |
塗装:約100万円 ※面積、屋根勾配、塗料の種類など によって異なる 「屋根の目安の金額」を参照 |
メンテナンスは、屋根になにを選ぶかによって大きく変わります。
また、FRPなどを原料とした屋根材は、基本的にはメンテナンスフリーとなっているようです。
<スポンサードリンク>
樹脂製品ですので、塗装の退色や、経年劣化が無いかなどは気になりますが、
今後価格が下がれば、選択する方も増えてくるのではないでしょうか。
最終更新日 : 2011年12月28日
屋根材 以外の部位もチェックしてみてください。
********************
・ 外壁材の種類と比較
・ 窓の種類と比較
・ 断熱材の種類と比較
********************